日常生活の中で、人間が体を動かす際には主に5つの動作パターンが関わっています。それは、「押す動き」「引く動き」「スクワット動作」「ヒップヒンジ動作」、そして「回旋動作(抗回旋動作を含む)」です。これらの動作が組み合わさることで、私たちは複雑な動きをスムーズに行うことができます。
今回は、特に「引く動き(上肢プル動作)」について詳しく解説します。
TOP> ブログ
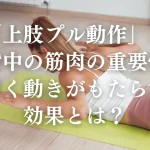
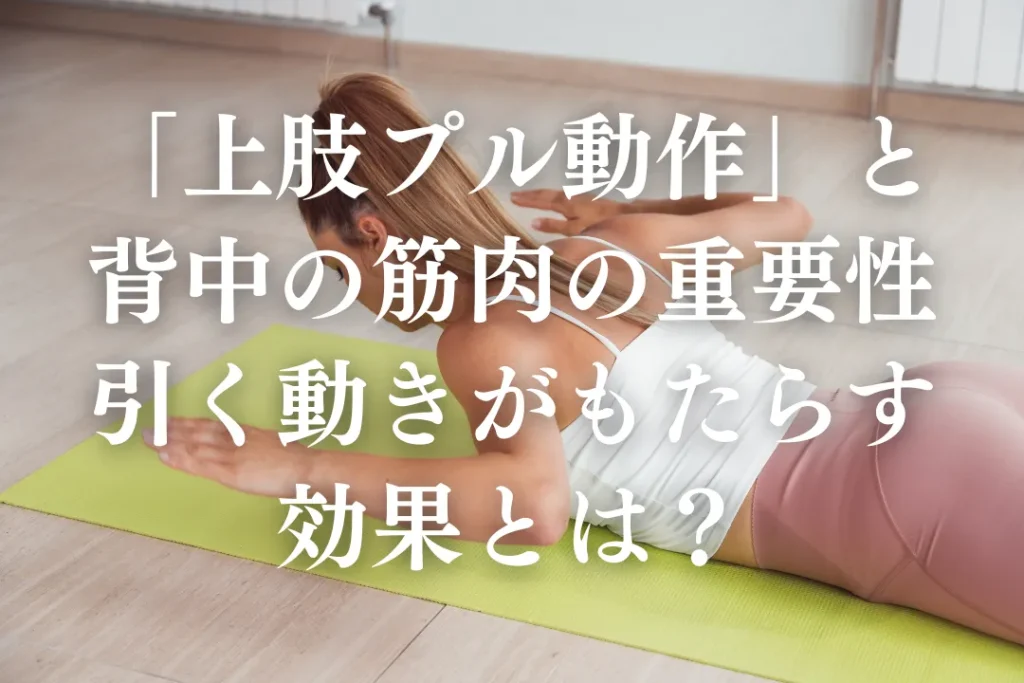
上肢プル動作は、何か物を前に「引く」動作を指します。例えば、ドアを手前に引いたり、ロープを引っ張ったりする動作がこれにあたります。日常生活でも頻繁に行われるこの「引く」動きですが、背中の筋肉が大きな役割を果たしています。
これらの動きは、全て「上肢プル動作」に該当します。
上肢プル動作において最も重要なのが背中の筋肉です。背中の筋肉は、広背筋や僧帽筋など、肩甲骨や背骨に付着している複数の筋肉群から成り立っています。これらの筋肉が一体となって働くことで、「引く」動作がスムーズに行えるようになります。
もし背中の筋力が低下していると、肩や腰に余分な負担がかかり、最終的には肩こりや猫背の原因になる可能性があります。
私たちは常に地球上で重力の影響を受けています。そのため、背中の筋肉が弱いと、重力に負けて自然に前かがみになりやすくなります。特に、スマートフォンやパソコンを長時間使用する現代では、頭が前に出て肩が丸まり、猫背や肩こりの原因になることが多いです。
背中の筋肉がしっかり働くことで、姿勢を正しく保つことができ、重力に逆らって体を支えることが可能になります。特に、肩甲骨周りの筋肉が機能していないと、肩が内側に入りやすくなり、肩こりや姿勢の悪化を招く原因となります。
現代の多くの人が悩む「姿勢の崩れ」は、背中の筋肉が十分に働いていないことが原因の一つです。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用で前かがみの姿勢が続くと、肩や首、背中に不自然な負担がかかります。
これを改善するためには、背中の筋力強化とストレッチが不可欠です。特に、「引く動作」を日常的に取り入れることで、背中の筋肉をバランスよく鍛え、姿勢を改善しやすくなります。
上肢プル動作は、日常生活の中でも頻繁に行われる基本的な動作の一つです。この動作において重要なのが、背中の筋肉の働きです。背中の筋肉がしっかりと働いていないと、肩こりや姿勢の悪化、猫背などの問題を引き起こすことになります。
正しい姿勢を保ち、日常生活で疲れにくい体を作るためにも、背中の筋力を意識して鍛えることが重要です。特に、デスクワークやスマートフォンの使用が多い現代人にとって、定期的に「引く動き」を取り入れ、背中を鍛えることが健康維持に大きく貢献します。
今後も日常生活の中で「上肢プル動作」を意識して、姿勢や体のバランスを整えていきましょう。

現在、初回体験トレーニング受付中です!
◎手ぶらで来店OK
◎入会金無料
◎当日入会で体験料無料
あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)
ーーーーーーーーーー
パーソナルジムビーユー
公式ホームページ
◯パーソナルジムビーユー田町芝浦・田町三田店
◯パーソナルジムビーユー大森店
◯パーソナルジムビーユー代々木上原店
https://beu.co.jp/yoyogi-uehara
【パーソナルジムビーユーで検索】
ビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。
・専属トレーナーによるマンツーマンサポート
・マニュアルのないあなただけのメニューを作成
・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク
・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間
・トレーニング後に毎回フィードバックを実施
・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料
会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!
あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。

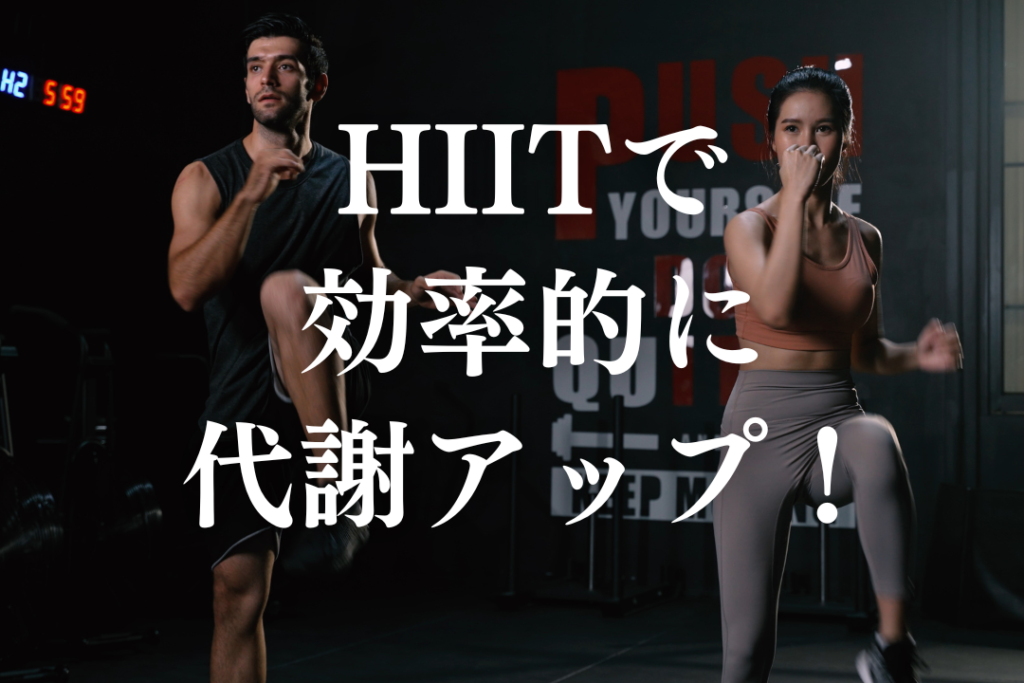
本日は、「HIIT(High Intensity Interval Training)」と呼ばれるトレーニング方法をご紹介します。
HIITはその名の通り、「高強度インターバルトレーニング」として、短時間で高い運動効果が期待できるトレーニングです。
忙しい中でもしっかりと体を動かしたい方や、効率よくカロリーを燃焼させたい方には特におすすめの方法です。
HIITの具体的なメリットや始め方について、詳しく解説していきます。

HIITとは、高強度インターバルトレーニングを意味し、20秒間の強度の高い運動を行い、その後10秒間の休憩を挟む、これを複数回繰り返すトレーニング方法です。
この短いサイクルの中で全力で動くことで、心拍数が上がり、効率的に体脂肪が燃焼されやすい体の状態を作り出します。
人間は、激しい運動をすると呼吸が乱れ、酸素が不足した状態になります。
これは体が「酸素を前借り」してエネルギーを補っている状態で、運動後も酸素消費が続き、体がその負債を返そうと働きます。
この運動後の酸素消費量が増える状態を「EPOC(運動後過剰酸素消費量)」と言い、一般的にはアフターバーン効果とも呼ばれています。
このEPOCがあると、運動を終えた後も代謝が上がった状態が続き、消費カロリーが増加する効果が期待できます。
HIITは、朝に行うことでさらに効果が高まります。朝に代謝が高まると、日中もその影響が続き、体がよりカロリーを消費しやすい状態がキープされます。
忙しい中でも短時間で運動効果を最大化したい方には、朝のHIITがオススメです。

HIITには、以下のような効果やメリットがあります。

HIITでは、年齢や運動レベルに合わせて目標心拍数が変わります。以下を参考にして、自分に合った強度で行うことが大切です。
無理のない強度から始めて、徐々に負荷を上げていくと良いでしょう。
HIITは初心者にとって負荷が高い場合もあるため、まずは朝のランニングなどの軽い運動から始めることがおすすめです。20秒のランニング後に10秒休むといった形で、心拍数が上がりすぎない範囲で行います。また、慣れてきたら強度を少しずつ上げていくと効果的です。
HIITは効果的なトレーニングですが、負荷が高いため、以下の点に注意して行うことが重要です。
HIITは、短時間で効率よくカロリーを消費し、心肺機能や代謝を向上させるトレーニングとして、忙しい現代人にぴったりの運動法です。EPOC効果によって運動後もカロリー消費が続くため、朝に行えば一日を通じて代謝が高まり、ダイエット効果も期待できます。
まずは無理のない強度で始め、徐々に自分に合った強度を見つけていくことで、安全に効果的なトレーニングを行いましょう。
ビーユーでも、個々の体力や目標に合わせたトレーニングプランを提供していますので、興味がある方はぜひ体験してみてください!
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

現在、初回体験トレーニング受付中です!
◎手ぶらで来店OK
◎入会金無料
◎当日入会で体験料無料
あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)
ーーーーーーーーーー
パーソナルジムビーユー
公式ホームページ
◯パーソナルジムビーユー田町芝浦・田町三田店
◯パーソナルジムビーユー大森店
◯パーソナルジムビーユー代々木上原店
https://beu.co.jp/yoyogi-uehara
【パーソナルジムビーユーで検索】
ビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。
・専属トレーナーによるマンツーマンサポート
・マニュアルのないあなただけのメニューを作成
・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク
・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間
・トレーニング後に毎回フィードバックを実施
・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料
会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!
あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
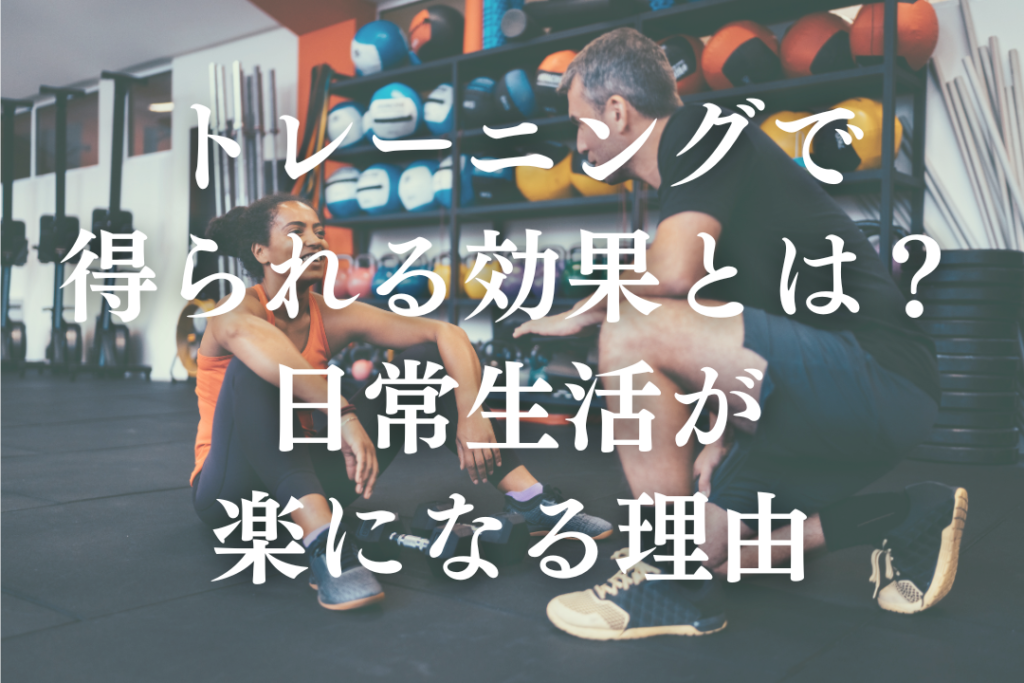
パーソナルジムビーユーでは、完全オーダーメイドでトレーニングメニューを提供しています。トレーニングの経験がない方から経験者まで、それぞれに合ったプログラムを作成し、一人ひとりの目標や体の状態に合わせたサポートを行います。
今回は、ビーユーに通われる62歳のトレーニング初心者の方を例に、トレーニングが日常生活にどのような影響を与えるのか、その効果を紹介します。年齢や運動経験に関係なく、体力や柔軟性が向上し、日常生活が楽になるトレーニングの効果についてご説明します。

この方はトレーニング初心者としてビーユーに入会され、最初は柔軟性が低かったため、基本的なストレッチや体幹トレーニングからスタートしました。トレーニングの初期段階では、無理に重い負荷をかけるのではなく、体を動かす基礎を築くことが重要です。ビーユーでは、個々の体の状態に合わせて土台作りを大切にしており、ストレッチや体幹トレーニングを通じて体がスムーズに動くようにサポートしています。
現在この方は、スクワット70kg、ベンチプレス50kg、デッドリフト60kgを扱えるまでに成長されました。トレーニング初心者でも、少しずつ基礎を築くことで、徐々にレベルアップが可能なのです。

「一般の方にここまでの筋トレが必要なのか?」と疑問に思うかもしれませんが、トレーニングによる恩恵は多くの方にとって有益です。筋力トレーニングを行うことで、日常生活での体力消費が少なくなり、体が楽に動かせるようになります。
例えば、日常生活で使う体力が「5」という値だと仮定します。トレーニングを行っていないAさんの体力キャパシティが「10」だとすると、日常生活で体力の半分(5/10)を使ってしまうため、疲れやすくなります。また、限られた体力を毎日消耗するため、しっかり寝ても体力が完全に回復しないことがあります。
一方で、ビーユーに通われているBさんはトレーニングによって体力キャパシティが「20」まで向上しています。日常生活で消費する体力がAさんと同じ「5」だったとしても、Bさんの場合、全体の4分の1しか消費しないため、余裕を持って体を動かせます。結果的に疲れにくく、体力回復も早くなるため、健康的な日常生活が送りやすくなるのです。

このように、体力キャパシティが増えると、日常生活における体の負担が軽減され、日々の動きがスムーズになります。また、トレーニングの効果はそれだけにとどまらず、以下のようなさまざまな利点が期待できます。
これらの効果が積み重なり、結果的に健康的で活力に満ちた生活が可能になります。高齢の方やトレーニング初心者の方でも、体力や柔軟性を徐々に向上させることで、日常生活が快適になります。

トレーニングの効果を最大限に引き出すためには、個々の体力や体調に合わせたオーダーメイドプログラムが重要です。無理な負荷や不適切なフォームでトレーニングを行うと、怪我のリスクが高まります。BeUでは、経験豊富なトレーナーが一人ひとりの状況に合わせて、柔軟にプログラムを設計し、安全に運動できるようサポートしています。
完全オーダーメイドのプログラムにより、初心者や高齢者の方でも安心して取り組むことができ、継続的に体力を向上させることが可能です。
パーソナルジムビーユーでは、完全オーダーメイドでトレーニングメニューを提供し、初心者や高齢の方でも無理なくトレーニングができるようサポートしています。体力キャパシティが増えることで、日常生活の負担が減り、疲れにくく、活動的な生活が送れるようになります。また、オーダーメイドプログラムにより、個々の体力や健康状態に合わせたトレーニングが行えるため、怪我のリスクも抑えられ、安全に体力を向上させることが可能です。
「日常生活をもっと楽にしたい」「健康的な体を維持したい」とお考えの方は、ぜひトレーニングを始めてみてはいかがでしょうか?
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

現在、初回体験トレーニング受付中です!
◎手ぶらで来店OK
◎入会金無料
◎当日入会で体験料無料
あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)
ーーーーーーーーーー
パーソナルジムビーユー
公式ホームページ
◯パーソナルジムビーユー田町芝浦・田町三田店
◯パーソナルジムビーユー大森店
◯パーソナルジムビーユー代々木上原店
https://beu.co.jp/yoyogi-uehara
【パーソナルジムビーユーで検索】
ビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。
・専属トレーナーによるマンツーマンサポート
・マニュアルのないあなただけのメニューを作成
・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク
・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間
・トレーニング後に毎回フィードバックを実施
・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料
会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!
あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽


ジムでのトレーニングは、体力向上やダイエット、健康維持のために効果的ですが、正しい姿勢で行うことがとても重要です。
間違った姿勢やフォームでトレーニングを続けると、筋肉や関節に負担がかかり、ケガをするリスクが高まります。
この記事では、ジムでのトレーニング中に正しい姿勢を保つ重要性と、ケガを防ぐために知っておきたいポイントを解説します。正しい姿勢でトレーニングを行い、安全に目標達成を目指しましょう!

ジムでトレーニングを行う際、正しいフォームを意識することは、筋肉や関節を保護し、ケガを予防するために非常に重要です。特にフリーウェイトや自重を使ったトレーニングでは、間違ったフォームが原因で痛みやケガにつながることが多いため、姿勢を整えることが必須です。

ジムでのトレーニングは種目によって姿勢が異なりますが、いくつかの基本ポイントを意識するだけでケガのリスクを減らし、効果的な運動が可能になります。代表的な種目ごとに正しい姿勢のポイントを見てみましょう。
スクワットは下半身全体を鍛える代表的なトレーニングですが、姿勢が崩れると膝や腰に負担がかかりやすくなります。
ベンチプレスは胸の筋肉を鍛えるエクササイズですが、正しい姿勢を意識しないと肩や肘に負担がかかりやすくなります。
プランクは体幹を鍛えるためのエクササイズですが、姿勢が崩れると腰や肩に負担がかかりやすくなります。

正しい姿勢を保つためには、ただフォームに気をつけるだけでなく、いくつかの工夫を取り入れると効果的です。以下の方法を取り入れることで、ケガのリスクを減らし、トレーニング効果を高めることができます。
トレーニング前のウォームアップは、筋肉や関節を温め、柔軟性を高めるために重要です。体が温まっていない状態で急に負荷をかけると、ケガのリスクが高まります。軽い有酸素運動や動的ストレッチを行い、トレーニングに適した体の状態を作りましょう。
筋力や体力を向上させるためには、トレーニング負荷を少しずつ増やしていくことが効果的です。しかし、無理に高い負荷をかけると、フォームが崩れやすくなりケガの原因になります。まずは軽めの負荷で正しいフォームをマスターし、慣れてきたら少しずつ重りや回数を増やしていきましょう。
ジムでのトレーニングが初めての場合や、フォームに不安がある場合は、パーソナルトレーナーの指導を受けることをおすすめします。プロのトレーナーがあなたの姿勢を確認し、正しいフォームでトレーニングできるようサポートしてくれます。また、自分だけでは気づきにくいフォームの癖や改善点も指摘してもらえるため、より効果的で安全なトレーニングができます。

ジムでのトレーニングでは、定期的に自分のフォームを見直すことが大切です。トレーニングに慣れてくると、姿勢が崩れていることに気づきにくくなるため、定期的にチェックを行うことで安全性が保たれます。
ジムでのトレーニングで成果を出すためには、正しい姿勢を保つことが欠かせません。姿勢を正すことで、ケガのリスクを減らし、トレーニングの効果を最大化することができます。ウォームアップや適切な負荷設定、定期的なフォームチェックを取り入れて、安全にトレーニングを続けましょう。
また、パーソナルトレーナーのサポートを受けることで、姿勢やフォームの改善がスムーズに進み、正しい姿勢が身につきやすくなります。ジムでのトレーニングは健康的な体づくりに大きな効果がありますが、正しい方法で行うことが何よりも大切です。正しい姿勢を心がけながら、ケガのない充実したトレーニングライフを送りましょう!
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

現在、初回体験トレーニング受付中です!
◎手ぶらで来店OK
◎入会金無料
◎当日入会で体験料無料
あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)
ーーーーーーーーーー
パーソナルジムビーユー
公式ホームページ
◯パーソナルジムビーユー田町芝浦・田町三田店
◯パーソナルジムビーユー大森店
◯パーソナルジムビーユー代々木上原店
https://beu.co.jp/yoyogi-uehara
【パーソナルジムビーユーで検索】
ビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。
・専属トレーナーによるマンツーマンサポート
・マニュアルのないあなただけのメニューを作成
・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク
・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間
・トレーニング後に毎回フィードバックを実施
・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料
会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!
あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
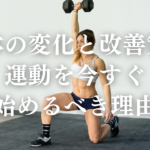
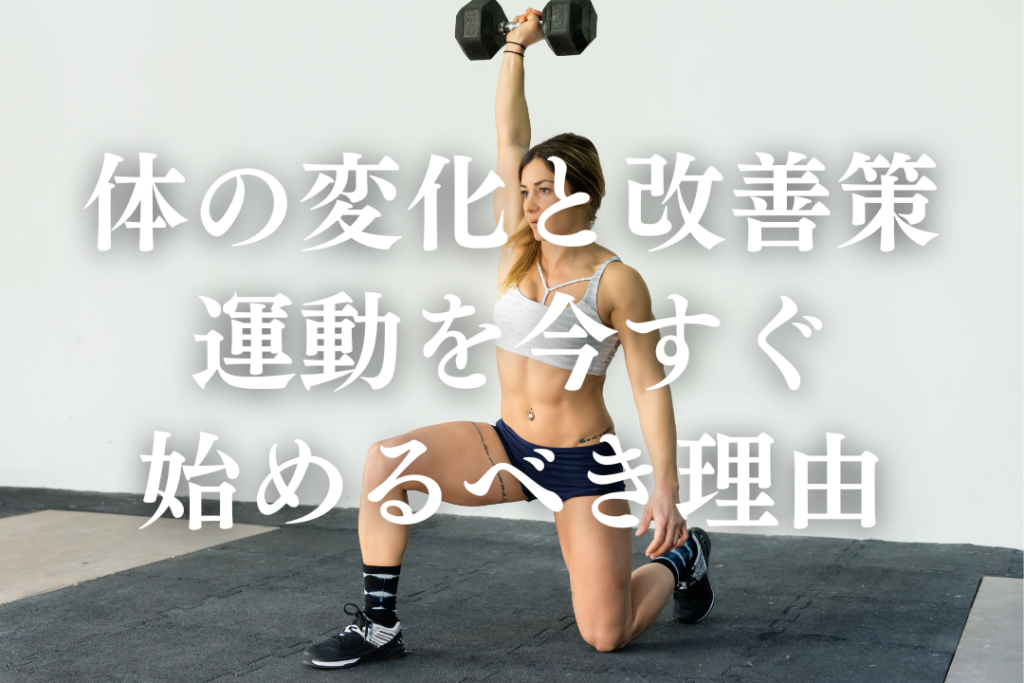
現代の生活は、デスクワークやスマートフォンの使用など、体を動かさない時間が増えています。このライフスタイルの変化によって、体にさまざまな影響が出始めています。姿勢の悪化、筋力低下、体重増加などの問題が蓄積されると、健康リスクが増加し、日常生活の質も低下してしまいます。
この記事では、現代のライフスタイルが体にどのような変化をもたらすのか、その改善策を紹介します。

長時間のデスクワークやスマホ操作で、猫背や前傾姿勢になる人が増えています。このような姿勢の悪化は、肩こりや腰痛を引き起こすだけでなく、内臓の位置が変わり、消化機能や呼吸にも悪影響を及ぼすことがあります。
•肩こりや腰痛:長時間の不自然な姿勢で筋肉が緊張し、コリや痛みを引き起こします。
•呼吸の浅さ:猫背になることで胸郭が圧迫され、呼吸が浅くなる傾向があります。これにより、十分な酸素を取り込めず、疲労感が増します。
•血行不良:姿勢が悪いと血流が滞りやすくなり、むくみや冷え性の原因になります。
•ストレッチと体幹トレーニング:姿勢を正すためには、柔軟性と体幹の筋力を鍛えることが重要です。デスクワークの合間に背筋を伸ばすストレッチや、プランクなどの体幹エクササイズを取り入れると良いでしょう。
•姿勢を意識した日常生活:座っている時や歩いている時に背筋を伸ばし、肩甲骨を引き寄せる意識を持つと、正しい姿勢が習慣化されやすくなります。
•定期的な休憩:1時間に1回は立ち上がり、体を動かして姿勢をリセットしましょう。これにより、筋肉の緊張をほぐし、姿勢を改善しやすくなります。

運動不足や年齢と共に、筋肉量が減少しやすくなります。筋力が低下すると、日常生活の動作がしづらくなったり、バランスを崩しやすくなったりします。筋肉は骨や関節をサポートするため、筋力の低下は腰痛や膝の痛みの原因にもつながります。
•転倒リスクの増加:筋力が低下するとバランスが取りにくくなり、転倒のリスクが高まります。
•代謝の低下:筋肉量が減ると基礎代謝が下がり、太りやすくなるため、肥満や生活習慣病のリスクも増えます。
•関節への負担:筋肉が関節を支えられなくなると、膝や腰などの関節に負担がかかりやすくなります。
•筋力トレーニング:筋トレを行うことで、体の筋肉量を維持または増やすことができます。初心者でも取り組みやすいスクワットやプッシュアップなどの自重トレーニングから始めると良いでしょう。
•バランストレーニング:片足立ちや体幹トレーニングなどのバランス系のエクササイズを取り入れると、筋力だけでなくバランス感覚も向上し、転倒予防につながります。
•日常の活動量を増やす:エスカレーターやエレベーターを使わず階段を使う、車を使わず歩くといった意識的に活動量を増やす工夫も、筋力維持に役立ちます。

現代の食生活では、カロリー摂取量が運動量を上回ることが多く、体重増加が深刻な問題となっています。体重が増加すると、肥満が原因となるさまざまな健康リスクが高まります。体脂肪が増えることで、生活習慣病や慢性疾患のリスクが増加するため、早めの対策が必要です。
•生活習慣病のリスク増加:体重増加により、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病リスクが高まります。
•関節への負担:体重が増えると、膝や腰にかかる負荷が大きくなり、関節痛の原因になることがあります。
•メンタルヘルスへの影響:体重が増加すると、自分に自信を持てなくなったり、ストレスを感じやすくなったりすることがあります。
•バランスの取れた食事:食事の内容を見直し、適切なカロリーと栄養を摂ることが大切です。高カロリーな食べ物や飲み物を控え、野菜やタンパク質をしっかり摂るよう心がけましょう。
•有酸素運動の取り入れ:ランニングやウォーキング、サイクリングなどの有酸素運動を定期的に行うことで、脂肪燃焼を促進し、体重管理がしやすくなります。
•日常の生活習慣の見直し:睡眠不足やストレスは、食欲の乱れや代謝の低下を引き起こす要因です。十分な睡眠をとり、ストレスケアも心がけて生活習慣を整えましょう。

現代社会では、ストレスが増加しており、それが体にさまざまな悪影響を及ぼしています。ストレスは、ホルモンバランスの乱れや免疫力の低下、さらには消化機能の低下にもつながります。ストレス管理を怠ると、心身の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
•ホルモンバランスの乱れ:ストレスがたまると、コルチゾールというホルモンが分泌され、体に疲労感やイライラが増えやすくなります。
•免疫力の低下:ストレスによって免疫機能が低下し、風邪や病気にかかりやすくなることがあります。
•睡眠の質の低下:ストレスが溜まると睡眠の質が下がり、疲労回復が遅れることがあります。
•リラクゼーションや趣味の時間:定期的にリラクゼーションを取り入れることや、趣味の時間を楽しむことが、ストレス軽減に役立ちます。
•呼吸法や瞑想:呼吸法や瞑想を取り入れることで、リラックス効果を得ることができます。1日数分からでも始めると、心身の緊張がほぐれてストレスが軽減します。
•定期的な運動:運動は、体にたまったストレスを発散するために効果的です。特に有酸素運動は、気分をリフレッシュさせ、リラックス効果をもたらします
現代社会におけるライフスタイルの変化によって、姿勢の悪化、筋力低下、体重増加、そしてストレスの増加など、私たちの体にはさまざまな変化が現れています。これらは日常生活や健康に大きな影響を及ぼすため、早めの対策が必要です。
姿勢を改善し、筋力を向上させることで、体の不調や怪我のリスクを減らし、生活の質を向上させることができます。また、適切な食事管理と定期的な有酸素運動で体重をコントロールし、生活習慣病の予防にもつなげましょう。さらに、ストレス管理を取り入れることで、心身ともに健康な状態を保つことができます。
このような改善策を少しずつ生活に取り入れることで、体の変化に対処し、より健康で活力ある毎日を送ることができます。今すぐできることから始めて、自分の体と心をいたわり、健やかな生活を手に入れましょう。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

現在、初回体験トレーニング受付中です!
◎手ぶらで来店OK
◎入会金無料
◎当日入会で体験料無料
あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)
ーーーーーーーーーー
パーソナルジムビーユー
公式ホームページ
◯パーソナルジムビーユー田町芝浦・田町三田店
◯パーソナルジムビーユー大森店
◯パーソナルジムビーユー代々木上原店
https://beu.co.jp/yoyogi-uehara
【パーソナルジムビーユーで検索】
ビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。
・専属トレーナーによるマンツーマンサポート
・マニュアルのないあなただけのメニューを作成
・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク
・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間
・トレーニング後に毎回フィードバックを実施
・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料
会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!
あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
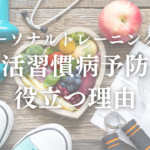

近年、生活習慣病のリスクが増加している現代社会において、健康維持や予防のための運動がますます注目されています。
生活習慣病は、不規則な食事や運動不足、ストレスなど、生活習慣の乱れが原因で発症する病気の総称です。
糖尿病、高血圧、肥満、心疾患などが代表的な病気で、放置しておくと重篤な健康問題につながる可能性があります。
そんな中、ジムでのパーソナルトレーニングが生活習慣病の予防に大きな役割を果たすことがわかっています。
この記事では、ジムでのパーソナルトレーニングがなぜ生活習慣病予防に効果的なのか、その理由を詳しく解説します。

生活習慣病予防のために最も重要なのは、継続的な運動習慣です。多くの人が、仕事や日常生活の忙しさの中で運動不足になりがちですが、パーソナルトレーニングを利用することで、定期的な運動を習慣化しやすくなります。
パーソナルトレーニングでは、トレーナーが一人ひとりの体力や生活習慣に合わせて、適切なトレーニングプログラムを作成してくれます。無理のない範囲で運動を始めることができ、少しずつ体力をつけていくことが可能です。また、目標を達成するために、定期的なフィードバックや調整が行われるため、効果的にトレーニングを進められます。
一人で運動を続けるのは難しいものです。パーソナルトレーナーのサポートがあれば、運動へのモチベーションが維持しやすくなります。定期的にトレーナーとセッションを行うことで、「今日はトレーニングの日だから行かなきゃ」という意識が働き、運動を習慣にしやすくなります。
ジムでのパーソナルトレーニングでは、個別指導のもとで正しいフォームや適切な負荷でトレーニングが行われるため、効果的に体力や筋力を向上させることができます。これにより、心肺機能や筋力の向上、代謝の促進が促され、生活習慣病のリスクを下げることが可能です。

パーソナルトレーニングでは、有酸素運動や筋力トレーニングを組み合わせて行うため、心肺機能を強化し、血圧の安定を促します。高血圧や心臓病などの生活習慣病は、血圧の管理が非常に重要です。運動によって心肺機能が向上することで、血圧のコントロールがしやすくなります。
ランニングやバイクエクササイズなどの有酸素運動を定期的に行うことで、心臓と肺の機能が強化されます。これにより、酸素の供給が効率的に行われ、血液の循環がスムーズになります。結果として、血圧が正常な範囲で保たれるようになり、心臓病や脳卒中のリスクが減少します。
筋力トレーニングは、筋肉量を増やし、基礎代謝を向上させる効果があります。筋肉が増えることで血糖値が安定し、糖尿病の予防に役立ちます。また、筋トレを行うことで血圧も管理しやすくなり、生活習慣病の予防に大いに役立ちます。

パーソナルトレーニングは、体脂肪の減少に効果的な運動メニューを組み込むことができるため、肥満の予防にも非常に役立ちます。肥満は生活習慣病のリスクを大幅に高めるため、体脂肪の管理が重要です。
パーソナルトレーナーが指導するトレーニングでは、脂肪燃焼効果が高いエクササイズを取り入れることが可能です。インターバルトレーニングやサーキットトレーニングなど、心拍数を上げつつも短時間で脂肪を効果的に燃焼するメニューを組むことで、効率的に体脂肪を減らすことができます。
筋力トレーニングを通じて筋肉量を増やすことで、基礎代謝が高まり、脂肪が燃焼しやすい体質へと変わります。これにより、太りにくい体質を作り上げることができ、長期的な健康維持が可能になります。特に、基礎代謝が高まることで、普段の生活でもカロリー消費が促進され、リバウンドを防ぐ効果も期待できます。

生活習慣病のリスクには、ストレスやメンタルヘルスの問題も大きく影響します。慢性的なストレスや精神的な負担は、血圧の上昇や血糖値の不安定化を招き、生活習慣病の引き金になります。パーソナルトレーニングを通じて、運動習慣をつけることで、ストレスを解消し、メンタルヘルスを向上させることができます。
運動を行うと、脳内で「エンドルフィン」と呼ばれるホルモンが分泌されます。このエンドルフィンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、気分を向上させ、ストレスを軽減する効果があります。定期的な運動は、ストレス解消に非常に効果的です。
パーソナルトレーナーと一緒にトレーニングを行うことで、運動に集中し、心身のリラックス効果を高めることができます。ジムでのトレーニングは、日常の忙しさから一時的に解放され、自分の体と向き合う時間を提供してくれます。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

現在、初回体験トレーニング受付中です!
◎手ぶらで来店OK
◎入会金無料
◎当日入会で体験料無料
あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)
ーーーーーーーーーー
パーソナルジムビーユー
公式ホームページ
◯パーソナルジムビーユー田町芝浦・田町三田店
◯パーソナルジムビーユー大森店
◯パーソナルジムビーユー代々木上原店
https://beu.co.jp/yoyogi-uehara
【パーソナルジムビーユーで検索】
ビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。
・専属トレーナーによるマンツーマンサポート
・マニュアルのないあなただけのメニューを作成
・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク
・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間
・トレーニング後に毎回フィードバックを実施
・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料
会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!
あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽


ジムに通うことを決めたら、次に考えるのは「どのトレーニングスタイルが自分に合っているか」ということです。
パーソナルトレーニングとグループフィットネスは、どちらも人気のあるトレーニングスタイルですが、それぞれにメリットがあり、効果的な目的や取り組み方も異なります。
この記事では、パーソナルトレーニングとグループフィットネスの違いと、それぞれがどのような場面で効果的なのかを解説します。

パーソナルトレーニングは、トレーナーが個別に指導してくれるマンツーマンのトレーニングスタイルです。
トレーナーが一人ひとりの目標や体力、ライフスタイルに合わせてトレーニングメニューをカスタマイズし、トレーニング中も細かく指導してくれるのが特徴です。
パーソナルトレーニングでは、あなたの体型や目標、健康状態に応じた完全オーダーメイドのメニューが作成されます。体重を減らしたい、筋力をつけたい、または特定の部位を引き締めたいといった、あなたのニーズに合わせたトレーニングが可能です。
トレーニング中、トレーナーが常にあなたの動きをチェックしてくれるため、正しいフォームでトレーニングを進められます。正しいフォームを習得することで、トレーニング効果を最大化し、怪我のリスクを軽減できます。
トレーニングの進捗状況に応じて、負荷やメニューの調整が随時行われます。例えば、トレーニングが進むにつれて筋力がついてくれば、トレーナーが強度を上げたり、異なるエクササイズを導入したりするので、飽きることなく続けやすいです。
トレーナーは、あなたのモチベーションを常にサポートしてくれます。運動が苦手な人でも、トレーナーの励ましやフィードバックがあることで、頑張る意欲を保ちやすくなります。また、パーソナルトレーニングは予約制が多く、スケジュールに組み込むことで習慣化しやすいです。

グループフィットネスは、複数の参加者と一緒に、インストラクターが指導するクラス形式のトレーニングです。ヨガ、エアロビクス、ボクササイズ、ダンス、ピラティスなど、さまざまなプログラムが提供されているのが特徴で、みんなで一緒に楽しく運動するスタイルです。
1. みんなで楽しみながら運動できる
グループフィットネスの最大の魅力は、複数の人と一緒に楽しく運動できることです。同じ目標を持った人たちと一緒にトレーニングすることで、互いに励まし合い、楽しみながら続けられるのが特徴です。
2. コストが比較的安い
パーソナルトレーニングに比べると、グループフィットネスは費用が安い傾向があります。クラス単位で参加費が設定されていることが多く、コストを抑えつつ、定期的に運動ができるのが魅力です。
3. 多様なプログラムで飽きない
グループフィットネスには、さまざまなプログラムが用意されているため、飽きずにいろんな運動に挑戦できます。ダンス系、リラクゼーション系、筋力強化系など、自分の気分や目的に合わせてクラスを選べるため、楽しく運動を続けられます。
4. 一体感がありモチベーションが上がる
クラスに参加する仲間と一緒にトレーニングすることで、一体感が生まれ、モチベーションがアップします。クラスの雰囲気に乗せられて、いつもより頑張れることも多いでしょう。

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

現在、初回体験トレーニング受付中です!
◎手ぶらで来店OK
◎入会金無料
◎当日入会で体験料無料
あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)
ーーーーーーーーーー
パーソナルジムビーユー
公式ホームページ
◯パーソナルジムビーユー田町芝浦・田町三田店
◯パーソナルジムビーユー大森店
◯パーソナルジムビーユー代々木上原店
https://beu.co.jp/yoyogi-uehara
【パーソナルジムビーユーで検索】
ビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。
・専属トレーナーによるマンツーマンサポート
・マニュアルのないあなただけのメニューを作成
・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク
・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間
・トレーニング後に毎回フィードバックを実施
・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料
会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!
あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽


ダイエットを成功させるために、ジムでのトレーニングは非常に効果的です。ただし、ジムに通うだけで必ずしも成功するわけではありません。重要なのは、正しい方法で取り組み、継続して努力することです。この記事では、ジム通いでダイエットを成功させるために欠かせない3つの重要な要素について解説します。これらの要素を意識することで、効果的に体脂肪を減らし、理想の体型を手に入れることができます。

ダイエットを成功させるためには、ただジムで運動するだけでなく、効果的なトレーニングプランを立てることが重要です。体重を減らすためには、筋トレと有酸素運動をバランスよく組み合わせることが大切です。
筋力トレーニングは、筋肉量を増やすことで基礎代謝を向上させます。基礎代謝が上がると、日常生活でも消費するカロリーが増え、痩せやすい体質に変わります。また、筋トレは脂肪だけでなく、筋肉を増やしながら体を引き締める効果もあるため、理想的な体型を目指す上で欠かせません。
有酸素運動は、体脂肪を効率よく燃焼させるために重要です。ジョギングやサイクリング、エリプティカルマシンなど、心拍数を上げながら長時間続けられる運動を取り入れることで、脂肪燃焼効果が高まります。有酸素運動は、筋力トレーニングと併用することで、ダイエットの結果を早く実感できるようになります。
ダイエットにおいて、筋力トレーニングと有酸素運動のどちらか一方に偏ってしまうと、効果が出にくくなります。筋肉をつけながら脂肪を燃やすために、バランスよくトレーニングプランを組み立てることが大切です。パーソナルトレーナーに相談して、自分に合ったプランを作ってもらうのも良い方法です。

どれだけハードにトレーニングをしても、食事管理ができていないとダイエットは成功しません。
食事は、ダイエットの成否を左右する大きな要素です。体に必要な栄養素をバランスよく摂取しながら、カロリーをコントロールすることが重要です。
ダイエットの基本は、摂取カロリーを消費カロリーよりも少なくすることです。つまり、1日の消費カロリーを超えないように、適切なカロリー量を摂取することが大切です。ただし、無理な食事制限は健康を害する可能性があるので、適度に行うようにしましょう。
カロリーを減らすだけでなく、栄養バランスも非常に重要です。筋肉を維持しながら脂肪を燃やすためには、タンパク質、炭水化物、脂質をバランスよく摂取することが必要です。特に、筋肉をつけるためにタンパク質の摂取が欠かせません。
トレーニング中に汗をかくことで水分が失われるため、十分な水分補給も大切です。水分不足は、代謝の低下や疲労感を引き起こし、ダイエットの進行を妨げる可能性があります。

ダイエットは、短期間で劇的な結果を得るのではなく、長期的に取り組む必要があります。そのため、ジム通いを続けるためのモチベーション管理が欠かせません。モチベーションが保てなければ、どんなに良いトレーニングや食事計画も無意味になってしまいます。
大きな目標を達成するためには、まず小さな目標を設定し、それをクリアしていくことが大切です。「1か月で体重を2kg減らす」「今週はジムに3回通う」といった具体的な目標を立てることで、達成感を得やすくなり、モチベーションが高まります。
同じトレーニングを繰り返していると、飽きてしまうことがあります。トレーニングに変化をつけたり、音楽を聴きながら運動したりすることで、楽しみながらジム通いを続けられます。また、友人やトレーニングパートナーと一緒にジムに通うことで、楽しい時間を共有し、励まし合うことができます。
パーソナルトレーナーにサポートを受けることで、トレーニングの効果を高めるだけでなく、モチベーションの維持にもつながります。トレーナーは、あなたの進捗を確認し、アドバイスをくれるだけでなく、目標に向けて一緒に取り組んでくれるパートナーです。

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

現在、初回体験トレーニング受付中です!
◎手ぶらで来店OK
◎入会金無料
◎当日入会で体験料無料
あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)
ーーーーーーーーーー
パーソナルジムビーユー
公式ホームページ
◯パーソナルジムビーユー田町芝浦・田町三田店
◯パーソナルジムビーユー大森店
◯パーソナルジムビーユー代々木上原店
https://beu.co.jp/yoyogi-uehara
【パーソナルジムビーユーで検索】
ビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。
・専属トレーナーによるマンツーマンサポート
・マニュアルのないあなただけのメニューを作成
・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク
・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間
・トレーニング後に毎回フィードバックを実施
・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料
会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!
あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽


初めてパーソナルジムに通おうと考えている方にとって、「どんな準備が必要なのか?」という疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。
パーソナルジムでは、トレーナーが個々の目標に合わせたトレーニングメニューを提案し、丁寧にサポートしてくれます。これにより、通常のフィットネスクラブや自己流のトレーニングとは違った体験ができます。ただし、事前に特別な準備が必要かどうかは、ジムごとに提供するサービスや設備が異なるので確認しておくと安心です。
このブログでは、パーソナルジムで初めての体験を成功させるために必要な準備について詳しく解説します。
また、必要なものがジムで提供されるケースについても触れますので、これからジムに通いたい方はぜひ参考にしてみてください。

パーソナルトレーニングを始める前に一番大切な準備は、「目標設定」です。なぜジムに通いたいのか、どんな体型や健康状態を目指しているのかをはっきりさせておくと、トレーナーとのコミュニケーションがスムーズになりますよ。
具体的な目標を設定しておくことで、トレーナーがあなたのニーズに合ったトレーニングメニューを作りやすくなります。数値化できる目標(例えば、3か月で5kg減量など)や、長期的な目標を立てておくと、進捗がわかりやすくてモチベーションも保ちやすいです。

次に重要なのは、自分の体調や過去の病歴を確認することです。パーソナルジムでは、一人ひとりの健康状態に合わせたトレーニングプランを作ってくれますが、正確な情報を提供することで、無理のない安全なメニューを提案してもらえます。
初回カウンセリングでは、これらの健康情報をトレーナーに伝えることで、安全で効果的なトレーニングができるようになります。

パーソナルジムでのトレーニングには、動きやすいウェアとシューズが基本的に必要です。ただ、ジムによってはウェアやシューズを貸し出しているところもあるので、事前に確認しておくと荷物を減らせて便利です。
ジムによっては、ウェアやシューズを貸し出している場合もあります。事前にジムのサイトや問い合わせ窓口で確認しておくと、荷物が減って便利ですよ。

トレーニング効果を最大限に引き出すためには、トレーニング前後の食事や水分補給も大事です。ジムによってはプロテインドリンクや水分補給のためのドリンクが用意されている場合もありますが、基本的には自分で準備しておくと安心です。

パーソナルジムでは、初回体験の際にトレーナーとのカウンセリングが行われます。ここで目標や健康状態を確認し、今後のトレーニングプランを立てるための大切な時間です。

初めてのパーソナルジム体験が無事に終わったら、次のステップは「継続」です。パーソナルトレーニングは、一度体験するだけでは目に見える変化はあまり期待できません。トレーニングを継続していくことで、体力や体型に変化が現れ、最終的に目標達成へとつながります。ここでは、継続するための心構えや、ジム通いを続けるためのヒントをいくつか紹介します。

パーソナルジムでの初体験に向けて、しっかり準備をしておけば、よりスムーズにトレーニングを始めることができます。目標設定、健康状態の確認、適切なウェアやシューズの準備に加え、食事や水分補給も忘れずに意識しましょう。ジムによっては、ウェアやシューズ、ドリンクの準備が整っている場合もありますので、事前に確認しておくと便利です。
初回の体験は、トレーナーが個別にサポートしてくれるので、初心者の方でも安心して参加できます。大切なのは、体験後も無理なく続けていくこと。小さな目標を立て、トレーナーの指導を受けながら、自分に合ったペースでトレーニングを継続していきましょう。パーソナルトレーニングは、健康的な体づくりだけでなく、持続的な運動習慣をつける絶好のチャンスです。ぜひ一度、体験トレーニングにチャレンジしてみてくださいね!
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

現在、初回体験トレーニング受付中です!
◎手ぶらで来店OK
◎入会金無料
◎当日入会で体験料無料
あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)
ーーーーーーーーーー
パーソナルジムビーユー
公式ホームページ
◯パーソナルジムビーユー田町芝浦・田町三田店
◯パーソナルジムビーユー大森店
◯パーソナルジムビーユー代々木上原店
https://beu.co.jp/yoyogi-uehara
【パーソナルジムビーユーで検索】
ビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。
・専属トレーナーによるマンツーマンサポート
・マニュアルのないあなただけのメニューを作成
・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク
・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間
・トレーニング後に毎回フィードバックを実施
・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料
会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!
あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

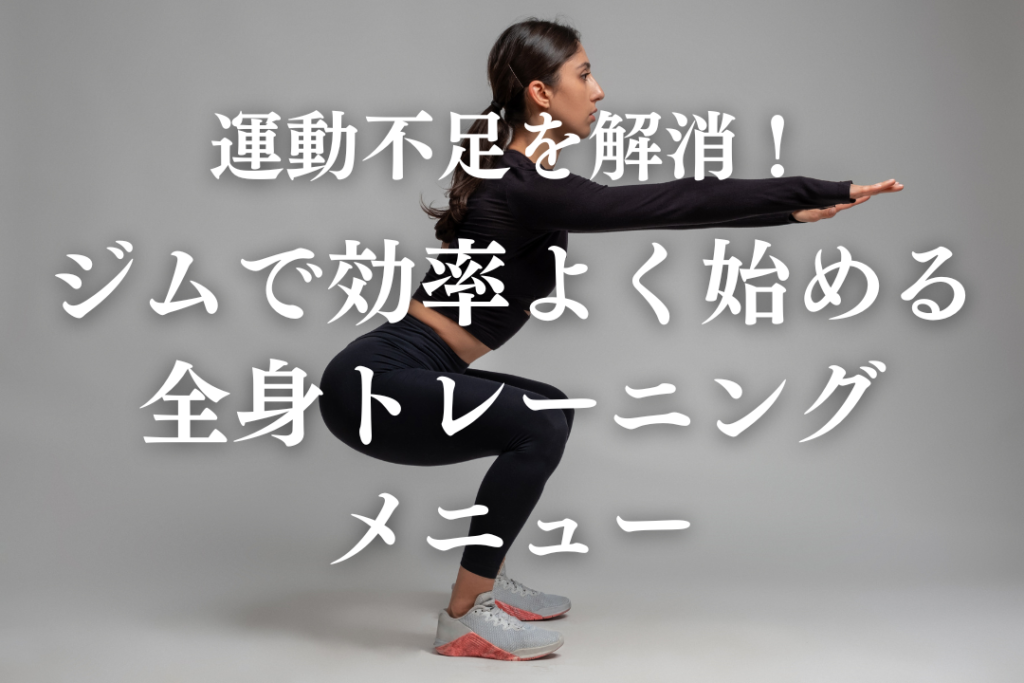
現代の生活スタイルでは、運動不足に悩む人が少なくありません。
特にデスクワークが多い方や、忙しい生活の中で体を動かす時間が取れない方にとって、体を動かすことが難しくなっています。
しかし、運動不足を放置すると、体力の低下や体重の増加だけでなく、健康にさまざまな悪影響を及ぼすことがあります。
この記事では、ジムで効率よく運動不足を解消し、全身を鍛えるためのトレーニングメニューをご紹介します。

運動不足は、体だけでなく心にも影響を与える大きなリスクです。
長時間座り続けることで、筋肉が弱まり、代謝が落ちるだけでなく、心血管系の健康やメンタルヘルスにも悪影響を及ぼすことが分かっています。
運動不足による主なリスクは以下の通りです。
運動不足を解消するためには、適切なトレーニングと生活習慣の改善が必要です。
ジムでのトレーニングは、効率よく全身を鍛え、健康的な体を手に入れるための最適な方法の一つです。

ボ運動不足を解消するためには、全身をバランスよく鍛えることが重要です。
特定の筋肉だけに偏ったトレーニングは、体のバランスを崩し、怪我のリスクを高める可能性があります。
ジムでのトレーニングでは、大筋群(脚、胸、背中など)を中心に、効率的に全身を鍛えることがポイントです。
ここでは、初心者でも取り組みやすい基本的な全身トレーニングメニューをご紹介します。

以下は、初心者でも取り組みやすい全身トレーニングメニューです。
週2〜3回を目安に行い、徐々に強度を上げていくことで、運動不足を解消しながら全身の筋力をバランスよく鍛えることができます。
スクワットは、全身を使う代表的なトレーニングで、特に脚や臀部の大筋群を効果的に鍛えます。
ベンチプレスは、胸や肩、腕の筋肉を鍛える効果的なエクササイズです。ジムではバーベルを使って行うのが一般的です。
ラットプルダウンは、背中の広背筋を鍛える運動です。姿勢を整え、背中全体を強化します。
プランクは、腹筋や背筋などの体幹を鍛えるトレーニングです。全身の安定性を高めるために有効です。
その他にもトレーニング方法はたくさんありますが、正しいフォームで行うことが重要です。
運動初心者の方は、まずはトレーナーに見てもらいながら行うことがおすすめです。

全身の筋肉を鍛えると同時に、脂肪燃焼を促進するためには有酸素運動も取り入れることが重要です。
有酸素運動は、心肺機能を向上させ、体全体の健康状態を改善します。
これらの有酸素運動は、筋トレ後に行うことで、脂肪燃焼効果をさらに高めることができます。
ランニングやバイクエクササイズでなくても、1駅分歩くようにしたり、日常の中で歩く意識をするだけでも、長期的には効果が出てきます。
まずは無理のない範囲で行うことが重要です。

運動不足を解消するためには、トレーニングを継続することが最も大切です。
短期間で大きな成果を期待するのではなく、少しずつ自分のペースで取り組むことが成功の鍵です。

運動不足を解消し、健康的な体を作るためには、全身をバランスよく鍛えるトレーニングが効果的です。
ジムでは、適切なメニューを実行することで効率的に筋肉を鍛え、心肺機能を高めることができます。
当ジムでは、初心者から経験者まで、パーソナルトレーナーが専属でサポートし、あなたに合ったトレーニングプランを提案します。
まずは体験トレーニングに参加して、運動不足を解消し、健康的なライフスタイルを手に入れましょう!
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

現在、初回体験トレーニング受付中です!
◎手ぶらで来店OK
◎入会金無料
◎当日入会で体験料無料
あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)
ーーーーーーーーーー
パーソナルジムビーユー
公式ホームページ
◯パーソナルジムビーユー田町芝浦・田町三田店
◯パーソナルジムビーユー大森店
◯パーソナルジムビーユー代々木上原店
https://beu.co.jp/yoyogi-uehara
【パーソナルジムビーユーで検索】
ビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。
・専属トレーナーによるマンツーマンサポート
・マニュアルのないあなただけのメニューを作成
・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク
・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間
・トレーニング後に毎回フィードバックを実施
・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料
会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!
あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽