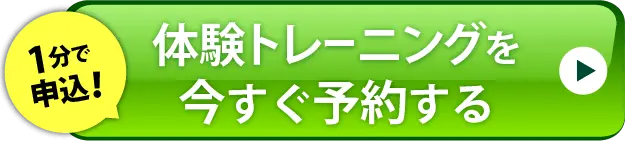-

パーソナルトレーニングが生活習慣病予防に役立つ理由
2024年10月4日トレーニングライフスタイルパーソナルトレーニングが生活習慣病予防に役立つ理由
近年、生活習慣病のリスクが増加している現代社会において、健康維持や予防のための運動がますます注目されています。
生活習慣病は、不規則な食事や運動不足、ストレスなど、生活習慣の乱れが原因で発症する病気の総称です。
糖尿病、高血圧、肥満、心疾患などが代表的な病気で、放置しておくと重篤な健康問題につながる可能性があります。
そんな中、ジムでのパーソナルトレーニングが生活習慣病の予防に大きな役割を果たすことがわかっています。
この記事では、ジムでのパーソナルトレーニングがなぜ生活習慣病予防に効果的なのか、その理由を詳しく解説します。
適切な運動習慣を確立できる
生活習慣病予防のために最も重要なのは、継続的な運動習慣です。多くの人が、仕事や日常生活の忙しさの中で運動不足になりがちですが、パーソナルトレーニングを利用することで、定期的な運動を習慣化しやすくなります。
適切なプログラムを作成
パーソナルトレーニングでは、トレーナーが一人ひとりの体力や生活習慣に合わせて、適切なトレーニングプログラムを作成してくれます。無理のない範囲で運動を始めることができ、少しずつ体力をつけていくことが可能です。また、目標を達成するために、定期的なフィードバックや調整が行われるため、効果的にトレーニングを進められます。
モチベーションを維持
一人で運動を続けるのは難しいものです。パーソナルトレーナーのサポートがあれば、運動へのモチベーションが維持しやすくなります。定期的にトレーナーとセッションを行うことで、「今日はトレーニングの日だから行かなきゃ」という意識が働き、運動を習慣にしやすくなります。
運動の効果を最大化
ジムでのパーソナルトレーニングでは、個別指導のもとで正しいフォームや適切な負荷でトレーニングが行われるため、効果的に体力や筋力を向上させることができます。これにより、心肺機能や筋力の向上、代謝の促進が促され、生活習慣病のリスクを下げることが可能です。
心肺機能の向上と血圧管理
パーソナルトレーニングでは、有酸素運動や筋力トレーニングを組み合わせて行うため、心肺機能を強化し、血圧の安定を促します。高血圧や心臓病などの生活習慣病は、血圧の管理が非常に重要です。運動によって心肺機能が向上することで、血圧のコントロールがしやすくなります。
有酸素運動による心肺機能の向上
ランニングやバイクエクササイズなどの有酸素運動を定期的に行うことで、心臓と肺の機能が強化されます。これにより、酸素の供給が効率的に行われ、血液の循環がスムーズになります。結果として、血圧が正常な範囲で保たれるようになり、心臓病や脳卒中のリスクが減少します。
筋力トレーニングで血糖値と血圧を管理
筋力トレーニングは、筋肉量を増やし、基礎代謝を向上させる効果があります。筋肉が増えることで血糖値が安定し、糖尿病の予防に役立ちます。また、筋トレを行うことで血圧も管理しやすくなり、生活習慣病の予防に大いに役立ちます。
3. 体脂肪の減少と代謝の向上
パーソナルトレーニングは、体脂肪の減少に効果的な運動メニューを組み込むことができるため、肥満の予防にも非常に役立ちます。肥満は生活習慣病のリスクを大幅に高めるため、体脂肪の管理が重要です。
効率的な脂肪燃焼
パーソナルトレーナーが指導するトレーニングでは、脂肪燃焼効果が高いエクササイズを取り入れることが可能です。インターバルトレーニングやサーキットトレーニングなど、心拍数を上げつつも短時間で脂肪を効果的に燃焼するメニューを組むことで、効率的に体脂肪を減らすことができます。
基礎代謝の向上
筋力トレーニングを通じて筋肉量を増やすことで、基礎代謝が高まり、脂肪が燃焼しやすい体質へと変わります。これにより、太りにくい体質を作り上げることができ、長期的な健康維持が可能になります。特に、基礎代謝が高まることで、普段の生活でもカロリー消費が促進され、リバウンドを防ぐ効果も期待できます。
4. ストレス軽減とメンタルヘルスの向上
生活習慣病のリスクには、ストレスやメンタルヘルスの問題も大きく影響します。慢性的なストレスや精神的な負担は、血圧の上昇や血糖値の不安定化を招き、生活習慣病の引き金になります。パーソナルトレーニングを通じて、運動習慣をつけることで、ストレスを解消し、メンタルヘルスを向上させることができます。
エンドルフィンの分泌促進
運動を行うと、脳内で「エンドルフィン」と呼ばれるホルモンが分泌されます。このエンドルフィンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、気分を向上させ、ストレスを軽減する効果があります。定期的な運動は、ストレス解消に非常に効果的です。
マインドフルネスな運動
パーソナルトレーナーと一緒にトレーニングを行うことで、運動に集中し、心身のリラックス効果を高めることができます。ジムでのトレーニングは、日常の忙しさから一時的に解放され、自分の体と向き合う時間を提供してくれます。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
体験トレーニング実施中

初回体験トレーニング 現在、初回体験トレーニング受付中です!
◎手ぶらで来店OK
◎入会金無料
◎当日入会で体験料無料あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)
ーーーーーーーーーーパーソナルジムビーユー
公式ホームページ
◯パーソナルジムビーユー田町芝浦・田町三田店
◯パーソナルジムビーユー大森店
◯パーソナルジムビーユー代々木上原店
https://beu.co.jp/yoyogi-uehara
【パーソナルジムビーユーで検索】
ビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。
・専属トレーナーによるマンツーマンサポート
・マニュアルのないあなただけのメニューを作成
・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク
・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間
・トレーニング後に毎回フィードバックを実施
・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!
あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
-
初めてのパーソナルジム体験:どんな準備が必要?
2024年9月28日トレーニングライフスタイル初めてのパーソナルジム体験:どんな準備が必要?
初めてパーソナルジムに通おうと考えている方にとって、「どんな準備が必要なのか?」という疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。
パーソナルジムでは、トレーナーが個々の目標に合わせたトレーニングメニューを提案し、丁寧にサポートしてくれます。これにより、通常のフィットネスクラブや自己流のトレーニングとは違った体験ができます。ただし、事前に特別な準備が必要かどうかは、ジムごとに提供するサービスや設備が異なるので確認しておくと安心です。
このブログでは、パーソナルジムで初めての体験を成功させるために必要な準備について詳しく解説します。
また、必要なものがジムで提供されるケースについても触れますので、これからジムに通いたい方はぜひ参考にしてみてください。
目標設定を明確にする
パーソナルトレーニングを始める前に一番大切な準備は、「目標設定」です。なぜジムに通いたいのか、どんな体型や健康状態を目指しているのかをはっきりさせておくと、トレーナーとのコミュニケーションがスムーズになりますよ。
よくある目標の例
- ダイエット:体重や体脂肪率を減らして、引き締まった体を作りたい。
- 筋力アップ:筋肉をつけて、より強く引き締まった体になりたい。
- 体力向上:全身の体力や持久力を高めて、日常生活をより快適に過ごしたい。
- 健康維持:生活習慣病の予防や、体のメンテナンスとして運動を取り入れたい。
具体的な目標を設定しておくことで、トレーナーがあなたのニーズに合ったトレーニングメニューを作りやすくなります。数値化できる目標(例えば、3か月で5kg減量など)や、長期的な目標を立てておくと、進捗がわかりやすくてモチベーションも保ちやすいです。
体調や健康状態のチェック
次に重要なのは、自分の体調や過去の病歴を確認することです。パーソナルジムでは、一人ひとりの健康状態に合わせたトレーニングプランを作ってくれますが、正確な情報を提供することで、無理のない安全なメニューを提案してもらえます。
確認しておきたいポイント
- 既往歴や慢性疾患:心臓病や高血圧、糖尿病などの持病があれば、トレーナーにしっかり伝えておくと安心です。
- 怪我の経験:膝や腰、肩に怪我をした経験があるなら、その影響を考慮したトレーニングメニューを組んでもらう必要があります。
- 現在の体調:運動が久しぶりだったり、体力に不安がある場合は、負荷の軽いメニューから始められるようトレーナーに相談しておきましょう。
初回カウンセリングでは、これらの健康情報をトレーナーに伝えることで、安全で効果的なトレーニングができるようになります。
ウェアとシューズの準備
パーソナルジムでのトレーニングには、動きやすいウェアとシューズが基本的に必要です。ただ、ジムによってはウェアやシューズを貸し出しているところもあるので、事前に確認しておくと荷物を減らせて便利です。
ウェアの選び方
- 動きやすさと速乾性:運動中は汗をかくので、速乾性のある素材(ポリエステルやナイロン)のフィットネスウェアを選びましょう。また、伸縮性があり、体の動きを妨げないものが理想的です。
- 快適さも大事:フィットしすぎないゆったりめのウェアや、体温調整しやすい服装を選ぶのもポイントです。
シューズの選び方
- クッション性とサポート力:足に負担がかからないよう、クッション性の高いシューズや、足首をしっかりサポートできるものを選ぶといいですよ。運動の種類によって、ランニングシューズやフィットネスシューズを使い分けるのもありです。
- ジムのルールを確認:一部のジムでは、シューズ不要の専用エリアや、シューズを脱いで行うトレーニングが提供されることもあります。事前に確認しておくと安心ですね。
ジムが準備している場合
ジムによっては、ウェアやシューズを貸し出している場合もあります。事前にジムのサイトや問い合わせ窓口で確認しておくと、荷物が減って便利ですよ。
食事と水分補給の準備
トレーニング効果を最大限に引き出すためには、トレーニング前後の食事や水分補給も大事です。ジムによってはプロテインドリンクや水分補給のためのドリンクが用意されている場合もありますが、基本的には自分で準備しておくと安心です。
トレーニング前の食事
- 炭水化物とタンパク質をバランスよく:運動前には、エネルギー源として炭水化物(ご飯やパン、フルーツ)を摂り、筋肉の回復を助けるタンパク質(鶏肉や卵、ヨーグルト)も一緒に摂ると良いです。
- 食事はトレーニングの1~2時間前に:消化に時間がかかる重たい食事は避けて、軽めの食事を1~2時間前に摂っておくと快適に運動できますよ。
水分補給
- こまめな水分補給が大事:運動中は汗をかくので、こまめに水分を補給しましょう。500ml~1L程度の水を持参して、少しずつ飲むのが理想的です。
- ジムのサービスを活用:ジムによっては、冷水機やスポーツドリンクが提供されていることもありますし、プロテインドリンクを購入できるところもあるので、必要であれば利用してみるといいですよ。
カウンセリングと体験当日の流れ
パーソナルジムでは、初回体験の際にトレーナーとのカウンセリングが行われます。ここで目標や健康状態を確認し、今後のトレーニングプランを立てるための大切な時間です。
カウンセリング内容
- 目標の確認:事前に考えた目標についてトレーナーと話し合い、短期的な目標と長期的な目標の両方を共有します。具体的な目標があると、トレーニングプランもより的確なものになりますよ。
- 健康状態のチェック:過去の怪我や病気の有無、現在の体調について詳しく伝えることで、あなたに合ったトレーニングメニューを提案してもらえます。
体験当日の流れ
- ウォームアップ:トレーニング前には、体を温めるためのウォームアップを行います。軽いストレッチや有酸素運動で、体をトレーニングに備えましょう。
- メイントレーニング:トレーナーと一緒に、あなたの目標に合わせた体験メニューを行います。トレーニングフォームも丁寧に指導してもらえるので、初心者でも安心です。
- クールダウン:トレーニング後には、体をリラックスさせ、筋肉をゆるめるためのクールダウンを行います。これには、軽いストレッチや呼吸を整える運動が含まれ、筋肉の疲労を和らげ、次の日の筋肉痛を軽減するのに役立ちます。ジムによっては、専用のリカバリーマシンやプロフェッショナルなストレッチの指導を受けられるところもあるので、ぜひ利用してみてください。
継続するための心構え
初めてのパーソナルジム体験が無事に終わったら、次のステップは「継続」です。パーソナルトレーニングは、一度体験するだけでは目に見える変化はあまり期待できません。トレーニングを継続していくことで、体力や体型に変化が現れ、最終的に目標達成へとつながります。ここでは、継続するための心構えや、ジム通いを続けるためのヒントをいくつか紹介します。
トレーニングは徐々にステップアップ
- 最初から無理をせず、体力や筋力に応じたトレーニングメニューを少しずつ増やしていくことが大切です。最初の数回は筋肉痛や疲れを感じることがありますが、無理せずペースを守れば徐々に体が慣れてきます。これがトレーニングの成功のカギになります。
成果は少しずつ出てくる
- トレーニングを始めてから最初に変化が現れるのは、2~3週間ほど経ってからと言われています。体重や体脂肪率の数値がすぐに大きく変わることは少ないですが、体の締まりや姿勢の改善を感じることができます。また、最初に筋力や体力の向上を感じやすくなるので、その小さな進歩を楽しみながら続けることがポイントです。
小さな目標を設定しよう
- 長期的な目標を設定するのは大切ですが、途中で小さな目標を作って達成感を感じることも重要です。例えば、「1か月で腕立て伏せを10回できるようになる」「3か月で体脂肪率を1%減らす」など、具体的で達成可能な目標を設けましょう。目標をクリアするたびに自信がつき、継続のモチベーションが高まります。
トレーナーに相談しながら進める
- モチベーションが下がったり、トレーニングに不安を感じたりした時は、遠慮なくトレーナーに相談しましょう。パーソナルトレーニングの一番の強みは、トレーナーがあなたを個別にサポートしてくれることです。体力や生活状況に応じてプランを柔軟に変更してくれるので、安心して進められますよ。
まとめ
パーソナルジムでの初体験に向けて、しっかり準備をしておけば、よりスムーズにトレーニングを始めることができます。目標設定、健康状態の確認、適切なウェアやシューズの準備に加え、食事や水分補給も忘れずに意識しましょう。ジムによっては、ウェアやシューズ、ドリンクの準備が整っている場合もありますので、事前に確認しておくと便利です。
初回の体験は、トレーナーが個別にサポートしてくれるので、初心者の方でも安心して参加できます。大切なのは、体験後も無理なく続けていくこと。小さな目標を立て、トレーナーの指導を受けながら、自分に合ったペースでトレーニングを継続していきましょう。パーソナルトレーニングは、健康的な体づくりだけでなく、持続的な運動習慣をつける絶好のチャンスです。ぜひ一度、体験トレーニングにチャレンジしてみてくださいね!
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
体験トレーニング実施中

初回体験トレーニング 現在、初回体験トレーニング受付中です!
◎手ぶらで来店OK
◎入会金無料
◎当日入会で体験料無料あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)
ーーーーーーーーーーパーソナルジムビーユー
公式ホームページ
◯パーソナルジムビーユー田町芝浦・田町三田店
◯パーソナルジムビーユー大森店
◯パーソナルジムビーユー代々木上原店
https://beu.co.jp/yoyogi-uehara
【パーソナルジムビーユーで検索】
ビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。
・専属トレーナーによるマンツーマンサポート
・マニュアルのないあなただけのメニューを作成
・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク
・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間
・トレーニング後に毎回フィードバックを実施
・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!
あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
-
足のむくみ解消!ふくらはぎのセルフケア
2024年4月10日ライフスタイル足のむくみ解消!ふくらはぎのセルフケア
足のむくみは、長時間の立ち仕事や座り続けるデスクワーク、さらには長距離のフライト後など、日常生活の多くのシチュエーションで経験される一般的な不快感です。
この不快なむくみは、血液循環やリンパ液の流れの乱れによって引き起こされます。
身体のリンパ系と循環系は、体内の液体バランスを維持し、廃棄物や毒素を排出するために密接に連携しています。
これらのシステムが適切に機能しないと、液体が組織に溜まり、結果としてむくみが発生します。
特定のセルフケア技術を用いることで、これらの症状を改善することができます。
今回紹介するのは、特にふくらはぎを中心としたセルフケア方法です。
ふくらはぎの筋肉は、血液循環にとって非常に重要な役割を担っています。
それは、心臓への血液の戻りを助けるポンプのような機能を果たしているため、「第二の心臓」とも称されます。
ふくらはぎの筋肉がしっかりと動作することで、下半身からの血液が心臓に戻りやすくなり、むくみの予防や改善につながります。
ふくらはぎセルフケアの具体的な方法
1. マッサージ
目的: 血液循環とリンパ流の促進
方法: ふくらはぎの筋肉を優しくもみほぐします。両手を使って、足首から膝に向かって、筋肉を包み込むようにして圧をかけながら上に向かって滑らせていきます。この動作を数回繰り返し、特に硬く感じる部分には少し長めに圧をかけます。動画はこちらから▼
https://www.instagram.com/reel/C5C4AKhS6vS/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
2. ストレッチ
目的: ふくらはぎの筋肉の柔軟性の向上
方法: 壁に手をつき、一方の足を後ろに伸ばしてかかとを床につけたまま、前の足を曲げて壁に体重をかけます。このポーズで、後ろの脚のふくらはぎが伸びているのを感じます。15~30秒キープした後、足を交換します。3. エレベーション(足の上げ)
目的: 血液とリンパ液の逆流を促進
方法: 寝転がって足を心臓よりも高い位置に上げます。例えば、枕やクッションを使って足を支えると良いでしょう。この状態を5~10分間キープします。
これらのセルフケア技術を日常生活に取り入れることで、足のむくみの軽減だけでなく、より健康的な血液循環を促進し、全身の健康維持に貢献することができます。重要なのは、これらの習慣を定期的に行い、生活の一部とすることです。日々のケアを通じて、足の不快感を解消し、活動的で健康的なライフスタイルを支えましょう。セルフエクササイズマニュアル(無料プレゼント)
自宅で行えるエクササイズプログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。
このマニュアルでは、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。
- 猫背
- 反り腰
- O脚
- ストレートネック
前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

 是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)
是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
体験トレーニング実施中
現在、初回体験トレーニング受付中です!
◎手ぶらで来店OK
◎入会金無料
◎当日入会で体験料無料あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)
ーーーーーーーーーーパーソナルジムビーユー
公式ホームページ
◯パーソナルジムビーユー田町芝浦・田町三田店
◯パーソナルジムビーユー大森店
◯パーソナルジムビーユー代々木上原店
https://beu.co.jp/yoyogi-uehara
【パーソナルジムビーユーで検索】
お客様の声
https://beu.co.jp/#voiceビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。
・専属トレーナーによるマンツーマンサポート
・マニュアルのないあなただけのメニューを作成
・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク
・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間
・トレーニング後に毎回フィードバックを実施
・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!
あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。まずは体験からお気軽にお問い合わせください^ ^
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
-
代謝の科学
2023年11月6日ライフスタイル代謝の科学
代謝は私たちの体が生きていく上で不可欠なプロセスです。
しかし、その複雑さと重要性にもかかわらず、多くの人にとって代謝の仕組みは謎に包まれています。
このブログでは、「代謝の科学」というテーマを掘り下げ、私たちの体がどのように食べ物をエネルギーに変え、細胞を構築し、健康を維持するのかを明らかにします。
代謝とは何か?
代謝(metabolism)という言葉は、ギリシャ語の「変化」や「変換」を意味する言葉に由来しています。
生物学的には、生命を維持するために生体内で行われる全ての化学反応のことを指します。
これらの反応は、栄養素をエネルギーに変換したり、細胞の構築と修復に必要な物質を合成したりするために不可欠です。
代謝は二つの基本的なカテゴリーに分けられます:異化代謝(カタボリズム)と同化代謝(アナボリズム)。
異化代謝は、大きな分子を小さな分子に分解し、エネルギーを放出するプロセスです。
同化代謝は、小さな分子から大きな分子を合成し、細胞の成長や修復に必要なエネルギーを消費するプロセスです。
代謝の基本
代謝経路
代謝経路は、生体内で特定の化学物質が別の化学物質に変換される一連のステップです。
代謝経路は非常に複雑で、多くの場合、複数の経路が相互に作用し合っています。
エネルギー代謝の中心:ATP
生命活動の通貨とも言えるアデノシン三リン酸(ATP)は、細胞内エネルギー代謝の中心です。
ATPは、エネルギーを必要とする反応で使用されると、アデノシン二リン酸(ADP)と無機リン酸に分解され、エネルギーが放出されます。
このエネルギーは、筋肉の収縮、細胞分裂、物質の輸送など、生体内の様々なプロセスに利用されます。
細胞は、食物から得た栄養素を使ってATPを再合成することで、このエネルギーを補っています。
代謝の調節機構
代謝は、細胞内外の様々なシグナルによって細かく調節されています。
例えば、インスリンやグルカゴンといったホルモンは、血糖レベルに応じて体内の糖代謝を調節します。
また、細胞のエネルギー状態を反映する分子(例:AMP、ADP)は、エネルギーを生産する代謝経路の活性の調節に関与しています。
このように、代謝は体が環境の変化に適応し、恒常性を維持するために制御されています。
※恒常性:体が内部環境を一定の範囲内で安定させる能力であり、温度、pH、電解質濃度などの生命維持活動を適切に維持すること。
代謝の種類
同化代謝(アナボリズム)
同化代謝、またはアナボリズムは、小さな分子から大きな分子を構築するプロセスです。
このエネルギーを要する過程は、細胞成長、修復、維持に不可欠で、筋肉の合成や細胞壁の構築など、体の構造的要素を作り出すために働きます。
例えば、アミノ酸からタンパク質を合成する過程は、アナボリズムの一形態です。
このプロセスは、エネルギーを蓄える形であり、ATPを消費して行われます。
異化代謝(カタボリズム)
異化代謝、またはカタボリズムは、大きな分子を小さな分子に分解し、この過程でエネルギーを放出するプロセスです。
この反応は、食物を消化し、栄養素をより小さな単位に分解して、細胞が利用可能なエネルギーを生成する際に重要です。
例としては、糖質がグルコースに分解され、さらに細胞呼吸によってATPを生成する過程が挙げられます。カタボリズムは、生体が活動するためのエネルギーを提供する基本的な方法です。
代謝と栄養
栄養素と代謝の関係
栄養素は代謝プロセスの基盤を形成します。私たちが摂取する食物は、炭水化物、脂質、タンパク質といったマクロ栄養素と、ビタミンやミネラルといったミクロ栄養素に分けられ、これらは体内で異なる代謝経路を通じて処理されます。マクロ栄養素は主にエネルギー源として利用され、ミクロ栄養素は代謝反応を助ける酵素や補酵素として機能します。
マクロ栄養素の代謝
炭水化物、脂質、タンパク質=マクロ栄養素は、それぞれ異なる代謝経路をたどります。
炭水化物は糖新生やグリコーゲン合成の形でエネルギーを蓄えるために利用され、脂質は脂肪酸の酸化によって大量のATPを生成します。
タンパク質はアミノ酸に分解され、エネルギー生成、新しいタンパク質の合成、または他の化合物への変換に利用されます。
ミクロ栄養素の役割
ビタミンやミネラルなどのミクロ栄養素は、体内での化学反応を促進する酵素の活性を助ける役割を持ちます。
これらは直接エネルギーを生み出しませんが、代謝を効率的に進行させるためには不可欠です。
例えば、ビタミンB群は多くの代謝酵素の活性化に関与しており、ミネラルは酵素の構造的要素や電解質バランスの維持に必要です。
運動と代謝
有酸素運動、筋力トレーニング、そして高強度インターバルトレーニング(HIIT)は、代謝を高めるために有効な運動です。
これらの運動が代謝に与える影響については、多くの研究が行われています。
有酸素運動
有酸素運動は、心臓と肺の機能を向上させ、全身の酸素と栄養素の供給を促進します。
これにより、細胞でのエネルギー代謝が活性化され、脂肪燃焼が効率的に行われるようになります。
『American Heart Association』によると、週に150分の中強度の有酸素運動は、成人の基礎代謝率(BMR)を向上させるのに役立ちます。さらに、運動後にはEPOC(余剰酸素消費後のエネルギー消費)効果が生じ、運動後もカロリー消費が続くとされています。
筋力トレーニング
筋力トレーニングは、筋肉量を増やすことで基礎代謝を上げる効果があります。
筋肉は安静時でもエネルギーを消費する組織であり、筋肉量が多ければ多いほど、日常生活でのカロリー消費量が増えるとされています。
『Medicine & Science in Sports & Exercise』誌に掲載された研究では、週に2〜3回の筋力トレーニングが基礎代謝率の向上に寄与することが示されています。
HIIT(高強度インターバルトレーニング)
HIITは、短時間で高い強度の運動を行い、その後に短い休息を挟むことで、EPOC効果を最大化します。
これにより、運動後も長時間にわたってカロリー消費が続くとされています。
また、HIITは成長ホルモンの分泌を促し、筋肉内のミトコンドリアの量と機能を向上させることで、長期的に基礎代謝率を高める効果があるとされています。
『Journal of Obesity』に掲載された研究では、HIITが代謝を高め、脂肪減少に効果的であることが示されています。
これらの運動は、代謝を下げる要因を逆転させる可能性があります。
例えば、加齢や運動不足による筋肉量の減少、不健康な食生活、ストレス、睡眠不足などが代謝を低下させる主な要因です。
有酸素運動、筋力トレーニング、HIITはこれらの代謝低下の要因に対抗し、エネルギー消費を高めることで、体重管理や全体的な健康の向上に寄与することができます。
食事と代謝
タンパク質の摂取
タンパク質の摂取が代謝に与える影響については、その熱産生効果(食事誘発性熱産生)が他のマクロ栄養素よりも顕著であることが科学的に支持されています。
『The Journal of Nutrition』に掲載された研究では、タンパク質の消化には脂肪や炭水化物に比べて約20-30%多くのエネルギーが必要であることが示されています。
これは、タンパク質が消化と吸収の過程で体の代謝を一時的に高めるため、体重管理に有効であるとされています。
さらに、タンパク質はレプチンの分泌を促進し、満腹感を長く保つことができるため、食事量の自然な抑制に寄与します。
食事回数
食事回数に関する研究はまちまちですが、一部の研究では小分けにした食事が血糖値の急激な上昇を防ぎ、終日のエネルギーレベルを安定させるのに役立つことが示されています。
しかし、これが代謝を高めるかどうかは明確ではなく、摂取カロリーの総量を管理することが重要です。
水分摂取
水分摂取が代謝に及ぼす影響については、『The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism』に掲載された研究で、水を飲むことで代謝が30-40%高まることが示されています。
特に冷たい水の摂取は、体が水を体温まで温めるために追加のエネルギーを消費するため、代謝をさらに促進する可能性があります。
ただし、胃腸に負担をかける可能性もあるため一気に冷たい水を飲むことは注意が必要です。
代謝を促進する食品
代謝を促進する食品に関しては、カプサイシン、カテキン、カフェインなどが含まれる食品が代謝を高めるとされています。
これらの成分は、体内でのエネルギー消費を一時的に増加させることが研究によって示されています。
例えば、『American Journal of Clinical Nutrition』に掲載された研究では、カプサイシンの摂取が一時的に代謝を高めることが確認されています。
これらを総合すると、タンパク質の摂取、適切な食事回数、十分な水分摂取、そして特定の成分を含む食品の選択が、代謝を高めるために有効です。
これらは、体重管理や全体的な健康維持にも役立つため、代謝を高めるためにも食習慣を整えることが大切です。
睡眠と代謝
睡眠と代謝の関係については、多くの研究が行われており、質の良い睡眠が代謝健康に不可欠であることが明らかになっています。
例えば、『Sleep』誌に掲載された2010年の研究では、短時間の睡眠が成人の肥満リスクを高めることが示されました。
この研究では、睡眠時間が短い人々はレプチンのレベルが低く、グレリンのレベルが高いことを発見しました。
レプチンは食欲を抑制し、満腹感を促すホルモンであり、グレリンは食欲を刺激するホルモンです。
このホルモンの不均衡は、食欲の増加とエネルギー消費の低下につながり、結果として体重増加に繋がります。
さらに、睡眠不足は体のインスリン感受性を低下させることがわかっています。
インスリンは血糖を細胞に取り込むことでエネルギーとして利用するためのホルモンですが、その感受性が低下すると、血糖が適切に利用されず、高血糖となります。
これは、代謝症候群や2型糖尿病のリスクを高める要因となります。
『Annals of Internal Medicine』誌に掲載された2012年の研究では、睡眠不足がインスリン感受性を低下させることが示されました。
睡眠不足はまた、エネルギー消費にも影響を与えます。
体はエネルギーを節約しようとするため、基礎代謝率(BMR)が低下することがあります。
これは、体が必要とする最小限のエネルギー消費が減少することを意味し、体重増加につながる可能性があります。
上記の通り、睡眠不足になることで代謝にも悪影響が出てしまうため、睡眠時間を確保することは非常に大切です。
まとめ
代謝は私たちの健康と活力に不可欠な役割を果たしています。
日々の生活の中で質の高い睡眠を確保し、バランスの取れた食事、適切な水分摂取、そして定期的な有酸素運動、筋力トレーニング、HIITを取り入れることで、代謝を活性化し、体の機能を最適化することができます。
これらの習慣は、長期的な健康維持において、小さな一歩として積み重ねることが大切ですので、毎日の習慣を作っていきましょう!
セルフエクササイズマニュアル(無料プレゼント)
自宅で行えるエクササイズプログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。
このマニュアルでは、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。
- 猫背
- 反り腰
- O脚
- ストレートネック
前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

 是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)
是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
現在、初回90分体験レッスン実施中です!
手ぶらOK/入会金無料/完全個室
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
現在、初回90分体験レッスン実施中です!
手ぶらOK/入会金無料/完全個室身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)
パーソナルジムビーユー
公式ホームページ
◯パーソナルジムビーユー田町芝浦・田町三田店
◯パーソナルジムビーユー大森店
◯パーソナルジムビーユー代々木上原店
https://beu.co.jp/yoyogi-uehara
【パーソナルジムビーユーで検索】
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
-
「いつ食べるか」を意識した時間栄養学で生活習慣を考えよう
2023年10月6日ダイエットライフスタイル食事「いつ食べるか」を意識した時間栄養学で生活習慣を考えよう
時間栄養学とは
時間栄養学とは、文字通り「いつ食べるか」ということに焦点を当てた栄養学の分野です。
伝統的な栄養学は「何を食べるか」に重点を置いてきましたが、近年の研究で「いつ食べるか」もまた健康や体調、パフォーマンスに大きな影響を与えることが明らかになってきました。
「いつ」食べるかによって、内臓脂肪や脂肪の付き方に違いが生じることがわかっています。
例えば、昼間よりも夜遅い時間に食事をすると、内臓脂肪の蓄積が促進される傾向があります。
この背後には、BMAL1というタンパク質が関係しています。
BMAL1は、私たちの体内時計を調節する時計遺伝子によって産生されるタンパク質で、このタンパク質の量は一日の中で変動します。
特に、夜の22時から夜中の2時頃にかけてBMAL1の量がピークを迎えるため、この時間帯に食事を取ると脂肪の蓄積が促進されてしまいます。
このように、食事のタイミングが私たちの体内にどのような影響を及ぼしているのか理解することで、自分の理想の体型に近づくヒントが得られるでしょう。
今回は、時間栄養学の視点から、私たちの日常生活や健康に与える食事のタイミングの影響を詳しく解説していきます。
サーカディアンリズムと食事の関連性
サーカディアンリズムとは、私たちの体内で約24時間の周期をもつ生理的、行動的リズムを指します。
このリズムは「体内時計」とも称され、太陽の光や温度、食事などの外部からのシグナルによって調整されています。
人の体内時計は、脳の視交叉上核という部位に存在し、この部分が様々なホルモンの分泌や体温、睡眠のリズムなどをコントロールしています。
例えば、朝日の光を浴びることで、体内時計は「朝」であると認識し、活動を始めるためのホルモンの分泌が促進されます。
そして、この体内時計と食事の関連性が近年注目されています。
特に、食事のタイミングがホルモンの分泌に与える影響は深いものがあります。
インスリンやグルカゴン、レプチンやグレリンなど、食事やエネルギー代謝に関わるホルモンの分泌は、食事のタイミングと密接に関連しています。
これらのホルモンは私たちの食欲やエネルギー利用、脂肪の蓄積などを調整しています。
適切なタイミングでの食事は、これらのホルモンバランスを最適化し、健康的な代謝をサポートします。
逆に、不規則な食事や夜遅くの食事は体内時計の乱れを引き起こし、代謝の低下や体重の増加、生活習慣病のリスクを高めることとなります。
夜間の食事と消化
私たちの身体は、夜間には消化機能が低下すると言われています。
これは、サーカディアンリズムに基づく体内時計の影響で、夜間には消化酵素の分泌が減少し、胃腸の動きも鈍くなるためです。
そのため、夜に重い食事を取ると、消化が遅れ、胃もたれや胸焼けなどの不快な症状を引き起こす可能性があります。
さらに、夜間の食事は、睡眠の質にも影響を及ぼすことがわかっています。
消化にエネルギーを使用することで、深い睡眠が妨げられ、熟睡感が得られなくなります。
特に、脂っこい食事やカフェインを多く含む飲み物は、睡眠の質を低下させます。
間食のタイミングと選び方
間食の背景には、多くの場合、血糖値の低下があります。
この低下は、身体がエネルギーを必要としているサインで、脳はそれを「空腹」として感じます。
食事の後、私たちの身体は炭水化物を糖に変え、それが血液を通じて身体中に運ばれます。
しかし、炭水化物の摂取が少ない時や食間の時間が長くなると、血糖値が低下し、それが空腹感や集中力の低下を引き起こします。
空腹感や血糖値の低下を効果的に管理するためには、賢い間食の選び方が必要です。
まず、高糖質のスナックや甘い飲み物は避けるよう心掛けましょう。これらは、短期間で血糖値を急上昇させるものの、すぐに急激に下がってしまいます。
そのため、繊維質やたんぱく質を含むものを選ぶと、血糖値が安定し、持続的なエネルギー供給が期待できます。
夜間のカロリー摂取が増えるよりは、間食を有効に使うことで血糖値が安定し過食を防ぐことが大切です。
トレーニングやスポーツと食事のタイミング
トレーニングやスポーツは、身体にとってエネルギーを多く使います。
運動前の食事は、身体が効果的にエネルギーを生み出す燃料になります。
一方、運動後の食事は、筋肉の修復や回復に必要な栄養になります。
そのため、筋トレを行う場合は筋トレ1〜2時間前におにぎりなどの糖質(エネルギー)を補給することがオススメです。
また、筋トレ後はタンパク質の多い食事を心がけることで、筋肉の修復・回復をしっかり行うことができます。
一方で、有酸素運動を行う場合、空腹状態で行うことで脂肪燃焼を促進しやすくなります。
ウォーキングなどの軽めの有酸素運動は減量・からだの引き締めに有効です。
食事のタイミングとダイエット
◉食事のタイミングがダイエット成功の鍵
ダイエットの成功は、食べる内容だけでなく、「いつ」食べるかというタイミングが非常に重要です。
適切なタイミングでの食事摂取は、基礎代謝を最適化し、脂肪の燃焼を促します。
一方で、不適切なタイミングでの食事は、脂肪の蓄積を助けることになり、ダイエットの効果を低下させてしまいます。
◉朝食の役割と重要性
朝食を摂ることで、脳の活動を活発にし、1日を通しての代謝も向上させます。
また、朝食で摂取したエネルギーは日中に使われるため、脂肪の蓄積もしにくいです。
ただし、前日に飲み会や食事をたくさん食べた場合は、胃腸を休める必要があるため体の状態を見て食事量を調整することが大切です。
◉夜食の影響
夜遅くの食事や夜食は、消化機能の低下とともに、エネルギーの消費も少なくなります。
そのため、夜に摂取したカロリーは脂肪として蓄積されやすくなります。
ダイエットを成功させるためには、夜の食事量を控えめにし、就寝の2~3時間前には食事を終えることがオススメです。
ダイエット成功のためには、食事の内容だけでなく、食事のタイミングもしっかりと意識することが必要です。
食事のタイミングを見直すことで、健康的な体重減少をサポートし、ダイエットの成功を実現する助けになります。
まとめ

時間栄養学の考え方を取り入れることは、健康維持や生活習慣病の予防だけでなく、ダイエットの成功にも非常に有効です。
食事の内容に気を付けることはもちろん大切ですが、それと同時に「いつ食べるか」というタイミングも考慮していきましょう。
特に、代謝の観点から見た食事のタイミングは、体重・体脂肪を減らすことにおいて重要な役割を果たします。
適切なタイミングでの食事は、基礎代謝を活性化させ、脂肪の燃焼を助けます。
逆に、不適切なタイミングでの食事は、脂肪の蓄積を促進するリスクが高まります。
また、ダイエットは一時的な取り組みではなく、長期的なライフスタイルの変化として捉えるべきです。
時間栄養学に基づく食事のタイミングを意識することで、健康的な生活習慣を築き、持続可能なダイエットを実現できます。
最後に、正しい知識をもとに、自身の生活リズムや体調に合わせた食事のタイミングを見つけ、健康的なダイエットを心がけることをおすすめします。
姿勢改善マニュアル(無料プレゼント)
姿勢改善に役立つ具体的な練習プログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。
今回は、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。
- 猫背
- 反り腰
- O脚
- ストレートネック
前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

 是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)
是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
現在、初回90分体験レッスン実施中です!
手ぶらOK/入会金無料/完全個室
あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)
パーソナルジムビーユー
公式ホームページ
◯パーソナルジムビーユー田町芝浦・田町三田店
◯パーソナルジムビーユー大森店
◯パーソナルジムビーユー代々木上原店
https://beu.co.jp/yoyogi-uehara
【パーソナルジムビーユーで検索】
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
-
筋トレと免疫
2023年10月3日トレーニングライフスタイル筋トレと免疫
免疫系は、体内の細菌やウイルスなどの外敵から私たちを守る役割を果たしています。
これは非常に複雑で、白血球、抗体、インターフェロンなどの成分が連携して機能しています。
そして、健康を維持するためには、この免疫システムが常に最適な状態でなければいけません。
筋トレというと、筋肉を鍛えることで引き締まった体を手に入れる、またはスポーツのパフォーマンスを向上させるためというイメージが強いかと思います。
しかしながら、近年の研究により、筋トレが免疫系を強化するメカニズムや、体の健康維持に寄与するメカニズムが明らかにされつつあります。
定期的な筋トレを行うことが、免疫系のバランスを整える効果があることが示されています。
また、筋トレによる代謝の向上や、筋肉から分泌される特定の物質が、免疫系の活性化に関係している可能性も研究されています。
この記事では、筋トレが免疫系に与える影響、そしてその背後にあるメカニズムについて解説していきます。
筋トレの効果を最大限に引き出すためのポイントや、過度な筋トレのリスクについても触れていきますので、健康的な生活を目指す方に、ぜひ参考にしていただければと思います。
筋トレが免疫を向上させる科学的根拠
筋トレが免疫系に与える影響について、以下の三つの点が特に注目されています。
1. 筋肉から分泌されるミオカイン
筋トレの際には筋肉から「ミオカイン」と呼ばれる種類のサイトカイン(細胞から分泌されるタンパク質)が分泌されます。
このミオカインは、免疫系の機能を正常に保つ役割があるとされ、特に感染症への抵抗力を向上させることが示唆されています。
2. ストレスホルモンの調整
筋トレは、ストレスホルモンの分泌を調整する効果があるとされています。
特に、コルチゾールというストレスホルモンの過剰な分泌は免疫系の機能を低下させる可能性があるため、筋トレによるその調整効果は、免疫系の健康にとって非常に重要です。
3. 体温上昇によるウィルスや細菌への抑制
筋トレを行うと、体内の筋肉が活動することで体温が一時的に上昇します。この体温上昇は、一部のウィルスや細菌の増殖を抑制する効果があり、免疫力の向上に寄与すると言われています。
筋トレの適切な方法と頻度
筋トレを行う際、その方法や頻度が非常に重要です。
適切な方法でトレーニングを行うことで、免疫向上の効果を最大限に引き出すことができます。
以下がメニューの例になります。
1. 初心者から上級者までのトレーニングメニュー
◯初心者
週に2~3回、全身を対象とした基本的な動作から始める。例: スクワット、プッシュアップ、プランクなど。◯中級者
週に3~4回、部位別のトレーニングや重量を加えたトレーニングを導入。例: ダンベルカール、ベンチプレス、レッグレイズなど。
◯上級者
週に4~5回、高強度インターバルトレーニング(HIIT)や専門的なトレーニング方法を取り入れる。
2. トレーニングの強度や回数の目安
適切なトレーニングの強度や回数は、目的や現在の体力レベルによって異なります。
しかし、免疫向上を目的とする場合、過度なトレーニングは避け、週に3~4回、各セット10~15回のトレーニングを心掛けるのがオススメです。
3.免疫向上に効果的なトレーニング部位
免疫向上を目的とする場合、大きな筋肉群を鍛えるトレーニングが効果的です。
特に、脚や背中を対象としたトレーニングは、多くのミオカインを分泌させるため、免疫向上に寄与すると言われています。
過度な筋トレのリスクと注意点
筋トレは免疫向上や健康の維持に役立つ反面、過度に行われると身体に悪影響を及ぼすこともあります。
以下に、そのリスクや注意点を詳しく解説します。
◎オーバートレーニング症候群とその症状
オーバートレーニング症候群は、筋トレやスポーツを過度に行い続けることで起こる状態です。
症状としては、持続的な疲労感、筋力や持久力の低下、免疫系の機能低下、睡眠の質の低下などが挙げられます。
◎筋トレのやり過ぎが免疫系に与える影響
筋トレの過度な継続は、一時的に免疫細胞の数や活動を低下させることが知られています。
これは、長期間の過度な筋トレが体を疲労させ、免疫系の機能を低下させるリスクを高める要因となります。
◎トレーニングの回復期間の重要性
筋トレの効果を最大化し、リスクを最小限にするためには、適切な回復期間を設けることが重要です。
特に、高強度のトレーニングを行った後は、48~72時間の休養が推奨されています。
まとめ
筋トレは、適切な方法で行うことで免疫系の強化や健康の維持に大きく役立ちます。
特に、筋肉から分泌されるミオカインや体温の上昇など、筋トレ特有の反応が免疫系に良い影響をもたらします。
さらに筋トレは、筋力や体力の向上だけでなく、日常生活の質を向上させる要因ともなります。
しかし、その効果を最大限に引き出すためには、適切な方法でのトレーニングと回復が不可欠です。
健康的な生活をサポートするため、筋トレの正しい知識と方法の理解をした上で実践していきましょう(^^)
姿勢改善マニュアル(無料プレゼント)
姿勢改善に役立つ具体的な練習プログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。
今回は、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。
- 猫背
- 反り腰
- O脚
- ストレートネック
前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

 是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)
是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
現在、初回90分体験レッスン実施中です!
手ぶらOK/入会金無料/完全個室
あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)
パーソナルジムビーユー
公式ホームページ
◯パーソナルジムビーユー田町芝浦・田町三田店
◯パーソナルジムビーユー大森店
◯パーソナルジムビーユー代々木上原店
https://beu.co.jp/yoyogi-uehara
【パーソナルジムビーユーで検索】
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
-

筋トレに最適な時間帯は「朝・日中・夜」いつ?
2023年9月27日トレーニングライフスタイル筋トレに最適な時間帯は「朝・日中・夜」いつ?

トレーニングに取り組む際、時間帯がトレーニングの効果にどれだけ影響を与えるのか、実際のところどうなのでしょうか?
多くの人が気にするこの疑問を解明するため、今回は筋トレの時間帯によるメリットとデメリットについてご紹介していきます。
朝のトレーニング
朝のトレーニングのメリット
まず、朝のトレーニングは新陳代謝をスピードアップさせます。
これにより、一日を通して消費されるカロリー量が増加し、脂肪燃焼効果が高まります。
また、トレーニング後のエンドルフィンの分泌により、朝から気分が良く、1日をスタートできます。
加えて、空腹時のトレーニングには、脂肪燃焼を促進する効果が期待できます。
空腹時の運動によって、体はエネルギー源として脂肪を優先的に使おうとします。
これは、特に体脂肪率を下げることを目的とする方々にとっては嬉しい一面です。
ただし、負荷の高いトレーニングを空腹時に行うことは低血糖を招き、貧血やめまいになりかねません。
空腹時の運動は、軽めの有酸素運動や軽負荷のトレーニングを選びましょう。
もし負荷の高いトレーニングを行う場合は、必ず糖質を補給して行うようにしてください。
朝のトレーニングのデメリット
朝の時間帯は筋肉が硬く、柔軟性が低下しています。
これは、筋肉の怪我や筋肉を痛めるリスクを高める可能性があります。
また、朝は体温が低く、筋肉や関節の動きが制限されやすくなります。
そのため、朝のトレーニングを行う際には、十分なウォーミングアップとストレッチが不可欠です。
日中のトレーニング
日中のトレーニングのメリット
多くの人は日中は活動的になり、身体的・精神的なピークを迎えます。
夜よりも目が覚めている時間帯なので、集中力や運動能力が高まりやすいです。
このピーク期間中に運動することで、トレーニングの質と効果を高めることが期待できます。
また、朝食や昼食後は、体にエネルギーがしっかり供給されているため、このエネルギーをトレーニングに利用することで、より高強度の運動に耐えることができ、筋トレの効果を高めることができます。
加えて、昼休みや空き時間にトレーニングをすることでリフレッシュができ、ストレスを発散することができます。
適度な運動は心身をリフレッシュさせる効果があり、仕事の生産性を高める助けとなります。
日中のトレーニングのデメリット
多くの人は日中に仕事や他の予定が詰まっているため、トレーニング時間が制限される場合があります。
十分なトレーニング時間を確保することが難しい場合、短時間での効率的なトレーニング方法を考える必要があります。
また、ジムに行かずに職場や自宅などの環境は、トレーニングに適していない場合が多いです。
このような場所でのトレーニングを考える際は、周囲の環境を整えましょう。
もし整えるのが難しい場合はジムの利用を積極的に行いましょう。
夜のトレーニング
夜のトレーニングのメリット
夜は仕事やその他の日常の予定から解放されることで、自分の時間を確保しやすくなります。
この時間を活用して、トレーニングに集中することができ、十分な時間を確保することができます。
加えて、筋トレは深い睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を促進するため、適度な運動は睡眠の質を向上させ、疲労回復やリカバリーを助けます。
さらに、適度な筋トレやストレッチは、一日の疲れやストレスを和らげる役割を果たします。
特に、深い呼吸を組み合わせた動きを取り入れることで、心身ともにリラックスすることができます。
夜のトレーニングのデメリット
高強度のトレーニングや心拍数を高める運動を行った後、興奮状態になるため、入眠に時間がかかる可能性があります。
そのため、寝る1~2時間前は高強度のトレーニングを避けたほうが良いです。
夜のトレーニング後には適切なクールダウンやリカバリーの時間を確保して、身体をリラックスモードにすることが大切です。
また、夜のトレーニング後のエネルギー消費が増えると、空腹感を感じやすくなり、夜食の誘惑が強まることがあります。
適切な食事計画や栄養補給の方法を取り入れることで、食欲をコントロールすることが大切です。
生活リズムに合わせた習慣づくり
生活スタイルや日常のリズムは人それぞれのため、都合の良いトレーニングの時間帯も一人ひとり異なるでしょう。
そのため、トレーニングを日課として取り入れる際には、個人の健康状態や生活リズムも考慮することが重要です。
例えば、早朝型の人は朝のトレーニングが適しているかもしれませんが、夜型の人には夜のトレーニングが合っている場合があります。
さらに、健康状態や日常の予定、体調によっても、最適なトレーニングの時間帯は変わることが考えられます。
また、突発的なトレーニングよりも、日常のルーティーンとしてトレーニングを継続することが大切です。
ただし、頻繁にトレーニングを行うことが良いというわけではありません。
身体を休めることも非常に重要であり、レストデイを適切に取り入れることで、筋肉や関節の回復を助け、トレーニングの成果を実感することができます。
まとめ
筋トレに最適な時間帯は、科学的根拠や一般的な傾向を考慮しても、結局は個人のライフスタイルや生活リズムによって異なります。
朝、日中、夜、それぞれの時間帯にメリットとデメリットが存在しますが、最も重要なのは、自分自身の体調や生活のリズム、目的や目標を理解し、それに合わせた選択をすることです。
自分に合った筋トレの時間帯を見つけ、それを継続して取り組むことが、なりたいからだになる近道です(^^)
姿勢改善マニュアル(無料プレゼント)
姿勢改善に役立つ具体的な練習プログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。
今回は、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。
- 猫背
- 反り腰
- O脚
- ストレートネック
前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

 是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)
是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
現在、初回90分体験レッスン実施中です!
手ぶらOK/入会金無料/完全個室あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)
パーソナルジムビーユー
公式ホームページ
◯パーソナルジムビーユー田町芝浦・田町三田店
◯パーソナルジムビーユー大森店
◯パーソナルジムビーユー代々木上原店
https://beu.co.jp/yoyogi-uehara
【パーソナルジムビーユーで検索】
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
-
冷え性(手足の冷え)の改善方法とは?原因や症状
2023年9月18日ライフスタイル冷え性(手足の冷え)の改善方法とは?原因や症状
冷え性は、多くの成人が抱える問題です。
この状態は、単に不快であるだけでなく、慢性的な冷え性は健康にも影響を与える可能性があります。
この記事では、冷え性の原因から症状、そして効果的な改善方法について解説します。
冷え性の原因
血流の悪化
冷え性の最も一般的な原因とされる血流の悪化は、多くの要因に起因します。
ストレスや疲れ、運動不足などの生活習慣から、特定の疾患まで、多くの要素が影響を与えます。
1. ストレス
ストレスは交感神経を活性化させ、これが血管を収縮させます。
継続的なストレス状態にあると、血流が悪化して冷え性の症状が出やすくなります。
2. 疲れ
疲れた状態では、体がリラックスと回復を促すために血流が内臓に集中し、手足への血流が減少します。
3. 運動不足
運動することで心拍数が上がり、血流が良くなります。
逆に、運動不足は血流の悪化を招きます。
生活習慣の要因
生活習慣も冷え性に大きな影響を与えます。
1. 運動不足: 前述したように、運動は血流を良くする効果があります。
2. 栄養不足: 鉄分やビタミンが不足すると、体温を適切に保つ能力が低下します。
3. 過度なダイエット: カロリーが不足すると、体はエネルギーを保存しようとして血流が低下します。
4. 不規則な生活リズム: 睡眠不足や過度なストレスは、自律神経を乱し血流を悪化させる可能性があります。
その他の医学的原因
一部の疾患や薬物も、冷え性の症状を引き起こす可能性があります。
1. 甲状腺機能低下症: 甲状腺ホルモンが不足すると体温が低下し、冷え性につながる場合があります。
2. 貧血: 鉄分が不足して赤血球が減少すると、酸素と栄養素の運搬能力が低下し、結果として冷
え性になりやすくなります。
3. 薬物の影響: 高血圧治療薬や抗不安薬など、一部の薬物は血管を収縮させる作用があり、冷え性を引き起こす可能性があります。
なぜ女性に冷え性が多いのか
冷え性は男女問わず起こりますが、統計的には女性の方が冷え性に悩まされるケースが多いとされています。
では、なぜ女性は特に冷え性になりやすいのでしょうか。
ホルモンの影響
女性ホルモンは、体温をコントロールする一つの大きな要素です。
特に、月経周期で変動するプロゲステロンやエストロゲンのレベルが、体温に影響を及ぼすことが分かっています。
◯月経周期と体温: 生理前後で体温が低下し、中でも排卵期に体温が上がる傾向があります。
◯更年期: エストロゲンの減少により、体温が不安定になることがよくあります。
脂肪組織の違い
女性は一般的に皮下脂肪が多く、この脂肪組織が熱を保持しにくい体質につながる可能性があります。
◯熱の保持: 脂肪は熱を保持するのにあまり効率的ではないため、女性は寒さを感じやすいことが多いです。
◯対流と放射: 皮下脂肪が多いと、熱の対流や放射が低下し、その結果体温が低下しやすくなります。
筋肉量の違い
男性は一般的に筋肉量が多く、筋肉は熱を生成する主要な要素であるため、男性は体温を一定に保つ能力が高いとされています。
一方で女性は男性と比べて筋肉量が少ないため、冷え性になりやすい体質です。
1. 熱生成
筋肉が多いと、基礎代謝も高く、それによって生まれる熱で体温を一定に保つことができます。
2. 活動量
筋肉量が多いと、運動によっても熱を多く生成するため、体温の低下が抑えられます。
血行の違い
特に生理中や妊娠、更年期などで、女性は血行が悪くなりやすいとされています。
1. 生理的変化
生理中や妊娠では、血液の粘性が変わることがあるため、血行が悪化しやすいです。
2. ホルモン影響
更年期におけるホルモンの変動も、血管の収縮や拡張に影響を与え、血行を悪化させることがあります。
感受性の違い
女性は、環境の温度変化に対して敏感であると一般的に考えられています。
1. 感覚の差
女性は、体温変化に対する感覚が鋭い可能性があります。
2. 心理的要因
ストレスや疲れも、寒さを感じる閾値を下げることがあります。
女性が冷え性になりやすい多くの理由がありますが、それぞれの要因には対処方法が存在します。
例えば、ホルモンバランスを整える食事や運動、血行を改善するためのストレッチやマッサージなど、具体的なアプローチ方法は多岐にわたります。
このような点を踏まえ、女性特有の冷え性の原因とその対策についても考慮することが重要です。
冷え性の症状
冷え性にはさまざまな症状がありますが、一般的には下記のような症状が現れます。
手足の冷え
この症状は冷え性の最も一般的な表れで、特に寒い季節によく見られます。
1. 寒冷曝露
寒い環境にいると、体は生命維持のために血流を中心に集める傾向があり、手足の血流が減少します。
2. 不適切な衣服選び
素材や厚みが不適切な衣服は、体温を保つのに十分ではなく、手足が冷える原因になることがあります。
疲れやすさ
血流が悪いと、酸素や栄養素の運搬が効率的でなくなり、疲れやすくなります。
1. 酸素不足
体の各部位への酸素供給が不足すると、疲労感が高まる。
2. 栄養不足
血流が悪いと、必要な栄養素が体全体に行き渡らず、エネルギーの生産が低下します。
頭痛や肩こり
血流が悪化すると、特に頭と肩周辺の筋肉に疲労物質が溜まりやすくなります。
1. 筋緊張
頭痛や肩こりは、しばしば筋肉が緊張している状態から生じます。血流が悪いと、この緊張を和らげるのが難しくなります。
2. 疲労物質の蓄積
血流が悪いと、疲労物質が排出されにくくなり、それが頭痛や肩こりを引き起こします。
その他の関連症状
冷え性は、他の健康問題とも関連があります。
1. 皮膚のトラブル
血流が悪いと、皮膚の新陳代謝も低下します。これが乾燥やかゆみ、さらには皮膚病の原因にもなります。
2. 免疫力の低下
体温が低下すると、免疫機能も低下します。その結果、風邪や感染症にかかりやすくなる可能性があります。
以上のように、冷え性の症状は多岐にわたり、それぞれが生活の質に影響を与える可能性があります。したがって、症状を正確に把握し、その原因を突き止めることが重要です。適切な対策や治療を行うことで、冷え性の症状は改善可能です。
冷え性の改善方法
食習慣の改善
1. 食材の選び方
血行促進作用があるとされる食材、例えばジンジャーやにんにく、唐辛子を食事に取り入れましょう。
冬は鍋などがオススメです。
2. 緑茶や黒糖も効果的
緑茶に含まれるカテキンや黒糖に含まれるミネラルも血行を良くすると言われているため、冷えに効果的です。
3. バランスの良い食事
全体的な栄養バランスも重要です。ビタミンEやオメガ3脂肪酸も血流に良い影響を与えるため、魚や緑黄色野菜などを積極的に接種するように心がけてください。
運動習慣をつける
1. 有酸素運動
ウォーキング、ジョギング、水泳などの有酸素運動は心拍数を上げ、全身の血流を改善する効果が期待できます。
2. 運動時間
運動不足の人は最初は10~15分程度から始め、徐々に時間を延ばしていくと良いです。
週に3回以上を最初は目標にしてください。
3. ストレッチ
運動の前後や就寝前などにストレッチをすることで、筋肉が伸ばされて血流の状態を良くすることができます。
衣服や生活環境の工夫
1. 重ね着
体温を逃がさないように、重ね着を心がけましょう。
2. 適切な暖房
体温を保つために、室温を適切に管理しましょう。
オーバーヒートを避け、適度な温度で暖を取りましょう。
ストレス管理
1. リラクゼーションテクニック
深呼吸、瞑想、ヨガなどでリラックスし、ストレスをコントロールします。
2. 日常生活での工夫
ストレスの原因を特定し、それを減らす工夫も必要です。
まとめ
手足の冷えは多くの人が感じる不快な症状です。
しかし、この問題は多くの場合、生活習慣の改善や運動、食事などによって解消できます。
そのため、症状を感じたら、まずは自分の生活習慣を見つめ直し、必要な改善を行うようにしましょう(^^)
姿勢改善マニュアル(無料プレゼント)
姿勢改善に役立つ具体的な練習プログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。
今回は、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。
- 猫背
- 反り腰
- O脚
- ストレートネック
前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。


是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)
【姿勢改善マニュアル】
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
現在、初回90分体験レッスン実施中です!
手ぶらOK/入会金無料/完全個室あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)
パーソナルジムビーユー
公式ホームページ
◯パーソナルジムビーユー田町芝浦・田町三田店
◯パーソナルジムビーユー大森店
◯パーソナルジムビーユー代々木上原店
https://beu.co.jp/yoyogi-uehara
【パーソナルジムビーユーで検索】
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
-
年代ごとにおこる女性の体型変化の原因と対策
2023年9月17日ダイエットボディメイクライフスタイル年代ごとにおこる女性の体型変化の原因と対策
女性の体型は年代によって様々な変化があります。
これは単なる外見の問題だけでなく、健康や生活の質にも影響します。
一般的に、若い頃は筋肉量が多く代謝も活発ですが、年齢を重ねるごとに筋肉量は減少し、脂肪が蓄積しやすくなります。
これはホルモンバランスの変動、活動量の低下、生活習慣の変化などが理由です。
さらに、女性は出産、授乳、更年期など、生涯を通じて体が大きな変化を遂げる期間が男性に比べて多いのも特徴です。
このような体の変化は、体型だけでなく心の健康にも影響を与えるため、どのように対処すべきか理解することが重要です。
この記事では、年代ごとに女性の体型がどのように変化するのか、その原因と対策について解説していきます。
女性の体型変化の傾向
年々体型が変わってきた、今まではすぐに落ちていた体重が落ちなくなってきた、と多くの女性が悩まれています。
若い頃は筋肉量が多く、代謝も高いですが、年齢を重ねると筋肉量は減少し、体脂肪が増加しやすくなります。
また、ホルモンも体型に大きく影響します。
特に、女性ホルモンのエストロゲンは脂肪の蓄積と分布に影響を与え、月経周期や妊娠、更年期によってそのバランスが大きく変わります。
エストロゲンが低下すると、特に腹部に脂肪が蓄積しやすくなります。
また、生活習慣も影響しています。
運動量が少なく、高カロリーな食事が多いと、どの年代でも体脂肪は増加しやすくなります。
しかし、同じ生活習慣でも年齢が上がるにつれて代謝が低下するため、運動量や健康的な食習慣は体型維持に必要不可欠です。
以下の各セクションでは、30代、40代、50代以降の女性に焦点を当て、それぞれの年代での体型変化の傾向、原因、そして対策について詳しく解説していきます。
30代女性ー新たな課題
30代での体型の変化
30代になると、多くの女性が身体的な変化を感じ始めます。
この年代は特に、代謝が減少し、体重が増加しやすくなる時期です。
さらに、多くの女性がこの年代で出産を経験するため、体型に大きな変化が起きることが多いです。
30代の主な原因
30代で体型が変わる主な原因は二つあります。
第一に、年齢とともに基礎代謝が低下すること。
20代と比べて運動量が同じでも、燃焼するカロリー量が少なくなります。
これが、体重が増加しやすい一因となります。
第二の原因は出産です。
妊娠・出産は女性の体に大きな影響を与え、特に体重が増加しやすくなります。
産後も、母体は赤ちゃんのケアに多くのエネルギーを使うため、自分自身の体調や体型を管理する時間とエネルギーが限られがちです。
その結果、体型や体重が崩れやすくなります。
30代の対策
1. 運動量の調整
代謝が落ちるため、同じ量の運動では体重を維持することが難しくなります。
ここで大切なのは、運動の質を高めること。
有酸素運動だけでなく、筋トレを取り入れて筋力を高める・筋肉量を増やすことで、基礎代謝を高める方法が有効です。
2. 食事の見直し
代謝が低下するため、摂取するカロリーもそれに合わせて調整する必要があります。
特に糖質や脂質の摂取を控えめにし、タンパク質やビタミン、ミネラルが豊富な食事を心掛けましょう。
3. 出産とその後のケア
出産を経験した場合、産後の体型戻しには時間がかかることが多いです。
しかし、適切な運動と食事管理で、少しずつでも前の状態に近づけることは十分可能です。
この年代は出産などで体型が大きく変わることが多いため、早いうちからしっかりとした対策が求められます。
40代 – 更年期とその前後
40代での体型の変化
40代になると、更年期が近づき体の変化が一層明らかになることが多く、その影響で体型も大きく変わる場合があります。
特に、脂肪がつきやすく、同時に筋力も低下するため、以前と同じライフスタイルを続けていても体型を維持するのが難しくなる女性が増えます。
40代の主な原因
40代での体型変化の主な原因は以下の二つです。
1. ホルモンレベルの変動
40代に入ると、更年期に伴うエストロゲンなどのホルモンレベルが変動し、その影響で代謝が低下します。
これにより体脂肪が蓄積しやすくなる傾向があります。
2. 筋力の低下
年齢とともに筋肉の量が減少し、特に40代ではこの傾向が強まります。
筋力の低下は代謝にも影響し、それが体型にも直結します。
40代の対策
1. 運動量を増やす
筋力の低下を防ぐためには、筋トレを含む継続的な運動が必要です。
特に、大きな筋群に焦点を当てた筋力トレーニングが効果的です。
2. 食事の見直し
ホルモンの影響で代謝が低下する40代では、食事内容の見直しも必要です。
30代と同様に、低糖質、高タンパクな食事が推奨されます。
この年代での体型維持は、ホルモンレベルの変動と筋力の低下によって特に難しい時期であり、対策が必要です。
また、更年期の症状が強い場合、ホルモン補充療法が有効な選択肢とされています。
ただし、この治療にはリスクもあるため、必ず専門の医師と相談することが重要です。
50代以降 – 維持とケア
50代以降での体型の変化
50代以降も人生の新たなフェーズが始まり、体の変化はさらに加速する場合が多いです。
筋肉の萎縮が進みやすくなり、それによって基礎代謝が低下します。
また、骨密度の低下も進むため、体型だけでなく健康全体が大きな影響を受ける可能性があります。
50代以降の主な原因
50代以降で体型変化の主な原因は、以下の通りです。
1. 筋肉の萎縮
50代になると、さらに筋肉の減少が進む可能性が高く、これが代謝にも影響して体型が変わり易くなります。
2. 骨密度の低下
更年期が過ぎると、特に女性は骨密度が低下し易くなります。
これは体型だけでなく、骨折のリスクも高めます。
50代以降の対策
1. 栄養素の吸収に重点を置いた食事
骨密度の低下と筋肉の萎縮を抑制するためには、カルシウム、ビタミンD、高タンパクな食事が重要です。
特に、高齢者が多く摂取すべきとされるビタミンB12も意識的に摂るようにすると良いでしょう。
2. 低強度の運動
高齢になると、負荷が高すぎる運動は体に負担をかける可能性があります。
そのため、ウォーキングや軽めの運動、スイミングなどの運動がおすすめです。
これらの運動は関節に優しく、筋肉や心肺機能の維持にも効果的です。
この年代では、健康の維持と並行して体型も管理することが特に重要となります。
適切な食事と運動で、健康で美しい体型を維持しましょう。
まとめ
女性の体型は年代ごとに多くの変化があります。
それぞれの年代での体型の変化には、代謝率、ホルモンバランス、生活習慣など多くの要因が関わっています。
20代では成長期から大人への移行が主な焦点であり、30代では代謝の低下や出産などが体型に影響を与えます。
40代では更年期によるホルモンバランスの変化と筋力の低下が主な要因であり、50代以降は筋肉の萎縮と骨密度の低下が顕著になります。
それぞれの年代での体型管理は、年代特有の課題に応じた対策が必要です。
どの年代でも共通するのは「健康的な食生活と運動習慣」です。
年代ごとに変わる体の状態に適切に対応して、なりたい自分を手に入れましょう(^^)
姿勢改善マニュアル(無料プレゼント)
姿勢改善に役立つ具体的な練習プログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。
今回は、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。
- 猫背
- 反り腰
- O脚
- ストレートネック
前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。


是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)
【姿勢改善マニュアル】
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
現在、初回90分体験レッスン実施中です!
手ぶらOK/入会金無料/完全個室
あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)
パーソナルジムビーユー
公式ホームページ
◯パーソナルジムビーユー田町芝浦・田町三田店
◯パーソナルジムビーユー大森店
◯パーソナルジムビーユー代々木上原店
https://beu.co.jp/yoyogi-uehara
【パーソナルジムビーユーで検索】
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
-
重曹水について
2021年5月19日ダイエットライフスタイル食事重曹水について
皆さん、こんにちは。
田町のパーソナルジムBeU代表の高正です。
今年は梅雨が長くなるようですね。ジメジメとして嫌な気候ですが、睡眠・栄養・運動の3つを整えて、しっかりと自己管理をしていきましょう。
さて、本日は重曹水について話をしていきたいと思います。
皆さんは重曹は掃除だけでなく、食べることにも使えることをご存知でしたか?
実は、重曹は健康的な体作りをしていく上で、非常に助けてくれるものなんです。
今回は重曹を取り入れることのメリットと、実際に取り入れる際の注意点をお伝えしていきます。
重曹が体に与える効果
まず、重曹が私たちの体にどのような効果をもたらしてくれるのか?についてですが、
重曹、つまり炭酸水素ナトリウムは自然界や体にも存在している物質なんです。
そして、重曹はナトリウム化合物の中でも最も弱いアルカリの1つになります。
重曹は料理に取り入れることで、お肉を柔らかくしたり、ぬめり・臭みを取ることができるのですが、特に私がおすすめするのは、お水に重曹を溶かす「重曹水」です。
重曹水は、コップ1杯に重曹水をティースプーン半分ほど入れて作るのですが、日々の生活の中で重曹水を飲むことはメリットが多いんです。その代表例は下記のとおりです。
- 胃腸の改善:重曹のアルカリ性で胃酸を中和させることができるため、胃腸の乱れを解消することができます。
- 便秘解消:重曹が体に入ると胃の中で炭酸ガスが発生して、腸が刺激されます。それによって便通が改善されます。
- 疲労回復:重炭酸イオンが疲れの原因である水素イオンを体外に排出するため、疲労回復に効果的です。
- 殺菌・口臭の予防:重曹はぬめりや臭みを取る作用があるため、殺菌や口臭予防に効果的です。
- 代謝アップ:炭酸ガスが体内に入ると、血液中の二酸化炭素が増加するため、酸素を運ぶために血流が良くなり、結果として血行が促進されます。
これらの通り、重曹水を取り入れることは体に非常に良いですが、2つほど注意点があります。
- 食用の重曹を使用すること:掃除用の重曹は純度が低いため、純度の高い食用のものを選択してください。
- 1日3グラムを超えないようにすること:重曹には塩分が含まれるため、摂りすぎると塩分過多になってしまいます。1日3グラムは超えないようにしてください。
是非、毎日の習慣として、重曹水を取り入れてみてくださいね。
それでは、本日の話は以上になります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。